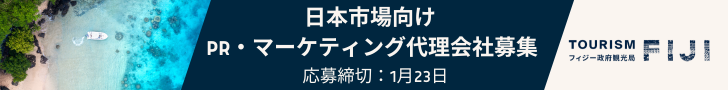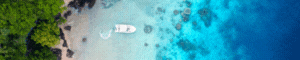脳と心のはたらきを知れば、コミュニケーションはもっと伝わる-縁多 日比野元哉氏
■安心がなければ、言葉は届かない
不安を感じているとき、人の脳は新しい情報を受け入れられません。「ミスしたら怒られるかも」「できなかったら評価が下がるかも」――そんな思いを抱えているとき、人は学べないのです。
だからこそ、支援者がまず提供すべきは「安心感」。その安心の土台の上にこそ、知識やスキルが根を張っていきます。
■"感性"という視点の重要性
最近、若い世代のスタッフと関わる中で感じるのは、彼らが情報収集や論理的思考には優れている一方で、「感じる力」や「他者の心を察する力」=感性が十分に育っていない場合もあるということです。
つまり、「知ってはいるが、感じていない」「理解はしているが、共感ができていない」といったギャップが生まれているのです。
縁多では、「知性を磨くと同時に、感性も育てる」ことを支援の核としています。スキルをいくら磨いても、それを"どう届けるか"、"相手がどう受け取るか"を考える力こそが、人材としての成熟につながると考えるからです。
■感性を育てるとは?
では、「感性を育てる」とは具体的にどういうことなのか?
感性とはセンスというよりも、"心の受信力"であり、他者との関係を築くための大切な土台です。次回はこの「感性」に焦点を当て、私たちはどうすればそれを磨けるのか、また組織の中でその力をどう育んでいけるのか、実例も交えてお話ししたいと思います。
■おわりに
「伝える技術」よりも、「伝わった」と感じてもらうためにはどうすればいいか——そのためには、心と脳、そして感性の理解が欠かせません。
支援とは、ただ正しさを伝えることではなく、「その人の中にある答え」に気づくきっかけを届けること。その姿勢こそが、成熟した支援者のあり方であり、チームが支え合える関係性の出発点なのだと、私は信じています。