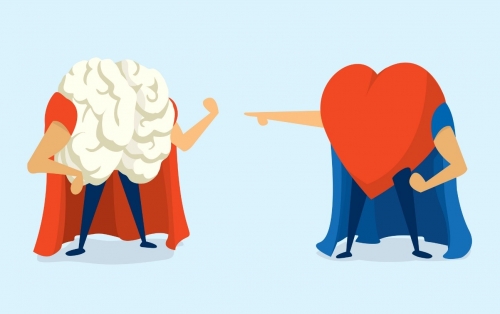脳と心のはたらきを知れば、コミュニケーションはもっと伝わる-縁多 日比野元哉氏
桜が散り、新緑がまぶしくなる季節となりました。人の動きも自然と活発になるこの時期、皆さまの職場でも新しい仲間を迎えたり、チーム体制に変化があったりする頃ではないでしょうか。
前回は、スタッフ一人ひとりに合わせてコミュニケーションを使い分けることの大切さについてお話ししました。今回はその続編として、「人間の脳と心のしくみ」に少し触れながら、なぜその使い分けが必要なのか、そしてどうやって見極めていくのかを掘り下げてみたいと思います。
■人の行動は「心」と「脳」がつくっている
人の行動は、意思だけでコントロールされているわけではありません。「気分の波」や「無意識の反応」が、私たちの言動に大きな影響を与えています。同じアドバイスでも、ある日はすんなり受け入れられるのに、別の日には抵抗を感じてしまう——これは、相手の「脳と心の状態」が日々変化しているためです。
脳には、次のような働きがあります。
- ●恒常性(ホメオスタシス):現状を維持しようとする性質
- ●感情の即時判断:まず感情(扁桃体)で反応し、その後に理性が働く
- ●習慣化による省エネ思考:考えるより慣れた行動を選びやすい
つまり私たちは、「変化を避けたい」「感情が先に立つ」「無意識に引っ張られる」存在なのです。
■人の行動が生まれるプロセス
- ①外部からの刺激(出来事・言葉・状況)
- ②感情の反応(扁桃体):「快」か「不快」かを瞬時に判断
- ③理性による評価(前頭前野):「大丈夫」「こうすればいい」と理屈で処理
- ④行動の選択
◦習慣的な反応
◦感情に影響された行動
◦自律的な判断と対応(コーチングによって可能になる)
■支援は「理屈」より「状態」へのアプローチ
前回ご紹介したように、支援には以下の3段階があります。
- ①Teaching(教育):正しい基準を示し、基本を教える
- ②Consulting(指導):失敗を一緒に振り返り、正解へ導く
- ③Coaching(自律):問いかけを通して気づきを促す
それぞれの段階で必要となる声がけは異なり、それは相手の"心理状態"を見極めるところから始まります。
例えば、「やる気がない」と見える人が、実は「不安」や「混乱」で動けない場合があります。逆に、意欲的に見えても、実は"空回り"していることもあるのです。だからこそ、支援者は"表面的な行動"だけでなく、"心と脳の状態"に注目する必要があります。
| 支援段階 | 心の状態 | 有効な声がけの例 |
|---|---|---|
| Teaching(教育) | 不安や緊張が強い | 「わからなくて当然です。安心して学べる場ですよ。」 |
| Consulting(指導) | 混乱や自信喪失 | 「何があったか一緒に整理しましょう。理由は必ずあります。」 |
| Coaching(自律) | 意欲的だが焦りがある | 「今のやり方、どう感じていますか?引っかかっていることはありますか?」 |