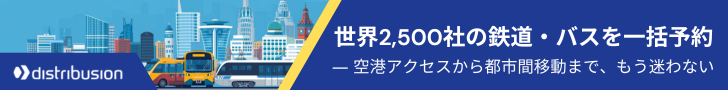DS模擬問題:ラオス編 ラオス伝統の食の魅力を屋台やマーケットで
問 ラオスの食事情で間違っているものは次のうちどれか
 A 料理によっては手で食べる
A 料理によっては手で食べる
B 麺料理は音をたてて食べてよい
C フランスパンがおいしい
D 泡盛のルーツといわれる焼酎がある
−−正解は下記へ
ココに注目!
▽ラオス伝統料理あれこれ
 旅行をする上で、圧倒的に情報量が少ないラオスにおいては、食事のイメージもわきにくい。ラオス料理は、隣国タイの料理にかなり近いと思っていいだろう。もともと、ラオスとタイは同系列の民族であるため、食事の内容も似ているのだ。
旅行をする上で、圧倒的に情報量が少ないラオスにおいては、食事のイメージもわきにくい。ラオス料理は、隣国タイの料理にかなり近いと思っていいだろう。もともと、ラオスとタイは同系列の民族であるため、食事の内容も似ているのだ。
ラオスの主食は米。それも、カオ・ニャオという呼び名のもち米だ。通常、ディップ・カオと呼ばれる竹細工の籠に入って出てくるので覚えておこう。おかずの定番はラープ。肉や魚のバージョンがあり、これに香草やレモン、ライムなどを入れて炒めたもの。鶏肉ならラープ・カイ、牛肉ならラープ・グア、魚ならラープ・パーというように呼び名が変わる。日本ともっとも異なる点は、これらを手で食べること。まず、もち米のカオ・ニャオをひと摘み手にとり、これにラープを合わせてつまむように口に運ぶのがラオスのスタイルとなっている。
また、屋台でよく見かける料理といえば、タム・マークフン。青いパパイヤを細切りにし、野菜と魚のエキスで味付けしたもので、要は炒め物だ。そのほか、ラオスの焼き鳥ピン・カイや魚の塩焼きピン・パーもポピュラーな料理だ。
 ラオスには麺料理も多い。これらは箸を使って食べるが、日本のようにズルズルと音をたてて食べるのは避けよう。代表的な麺料理は米から作る白い麺のフーで、ベトナムでいうフォーのこと。ほかにも、小麦粉で作る黄色い麺のミー、米と片栗粉から作るカオ・ピヤック・セン、素麺のような細いカオ・プンなど種類が多く、メニューも坦々麺風、焼きそば風と多種多様にそろっている。屋台ではインスタントラーメンも食べられるので、散策の途中で小腹を満たすこともできる。
ラオスには麺料理も多い。これらは箸を使って食べるが、日本のようにズルズルと音をたてて食べるのは避けよう。代表的な麺料理は米から作る白い麺のフーで、ベトナムでいうフォーのこと。ほかにも、小麦粉で作る黄色い麺のミー、米と片栗粉から作るカオ・ピヤック・セン、素麺のような細いカオ・プンなど種類が多く、メニューも坦々麺風、焼きそば風と多種多様にそろっている。屋台ではインスタントラーメンも食べられるので、散策の途中で小腹を満たすこともできる。
▽ラオス産のお酒とデザート
 フランスが統治していた名残で、フランスパンがおいしいのはベトナムと同様だ。ラオスのサンドイッチは、フランスパンにハムや野菜を挟み、醤油やチリソースで味付けするのが特徴。練乳入りのコーヒーと一緒に、ラオス風の朝食を楽しみたい。
フランスが統治していた名残で、フランスパンがおいしいのはベトナムと同様だ。ラオスのサンドイッチは、フランスパンにハムや野菜を挟み、醤油やチリソースで味付けするのが特徴。練乳入りのコーヒーと一緒に、ラオス風の朝食を楽しみたい。
また、ラオスの飲み物といえば、ラオ・ラーオ。沖縄の泡盛のルーツとされる米焼酎のことで、アルコール度数は高いもので40度以上もある。一度も蒸さずにつくるラオ・カーオ、一度蒸して水を加え数日置くラオ・サト、赤米でつくるラオ・カオ・カムの3種類がある。ラオ・ラーオは、ラオス全土で造られており、ツアーによっては酒造りの村へ立ち寄るコースもある。ラオスの国産ビールはビア・ラーオ。ライトビールや黒ビールもあり、乾いた喉を潤すのに最適だ。ちなみに、ビエンチャンの郊外にビア・ラーオ工場があり、予約すれば誰でも製造ラインの見学や試飲ができる。
ラオスの伝統デザートは、クレープ風、ドーナツ風、中華まん風と多彩だが、どことなく全体的に中華風だ。素材はとうもろこし、もち米、バナナ、練乳、ココナッツなど。バナナを焼いただけのクワイ・チーにも一度はトライしたい。ポピュラーなのは、みつまめ風のナム・ワーン。ココナッツミルクに色とりどりの寒天やゼリーが入っていて、ここにタピオカ、黒豆、角切りにしたサツマイモ、パイナップル、パパイヤなどのトッピングを入れて食べる。トッピングによって味が変わるので、毎日食べても飽きがこない一品だ。
▽本場の味なら屋台やマーケットへ
 首都ビエンチャンや観光客の多いルアンパバーンでは、ラオス料理をはじめ、ヨーロッパ料理、和食、中華、タイ料理、ベトナム料理と何でもそろっている。しかし、地元の人々の生活や活気に触れるという意味で、屋台やマーケットへぜひ足を運びたい。ビエンチャンなら、町一番の規模をほこる市場タラート・トンカンカムがお勧め。肉や魚、野菜などの生鮮食品がところ狭しと並ぶなか、屋台スペースでラオスの伝統料理が味わえる。そのほか、近代的な新館もある巨大マーケットのタラート・サオにはフードコート、庶民的な市場タラート・ノントゥアンでは屋台スペースがあり、市内中心部から足を運びやすい。
首都ビエンチャンや観光客の多いルアンパバーンでは、ラオス料理をはじめ、ヨーロッパ料理、和食、中華、タイ料理、ベトナム料理と何でもそろっている。しかし、地元の人々の生活や活気に触れるという意味で、屋台やマーケットへぜひ足を運びたい。ビエンチャンなら、町一番の規模をほこる市場タラート・トンカンカムがお勧め。肉や魚、野菜などの生鮮食品がところ狭しと並ぶなか、屋台スペースでラオスの伝統料理が味わえる。そのほか、近代的な新館もある巨大マーケットのタラート・サオにはフードコート、庶民的な市場タラート・ノントゥアンでは屋台スペースがあり、市内中心部から足を運びやすい。
ルアンパバーンなら、ナイトマーケットがいいだろう。国立博物館前のシーサワンウォン通りが歩行者天国になっており、5600メートルの道いっぱいに露天が並ぶにぎわいは地元のパワーを感じる圧巻の風景だ。食べ物の屋台も出ているので、食事目的で訪れても、そぞろ歩きの途中でデザートを楽しんでもいいだろう。

正解:B
 A 料理によっては手で食べる
A 料理によっては手で食べるB 麺料理は音をたてて食べてよい
C フランスパンがおいしい
D 泡盛のルーツといわれる焼酎がある
−−正解は下記へ
ココに注目!
▽ラオス伝統料理あれこれ
 旅行をする上で、圧倒的に情報量が少ないラオスにおいては、食事のイメージもわきにくい。ラオス料理は、隣国タイの料理にかなり近いと思っていいだろう。もともと、ラオスとタイは同系列の民族であるため、食事の内容も似ているのだ。
旅行をする上で、圧倒的に情報量が少ないラオスにおいては、食事のイメージもわきにくい。ラオス料理は、隣国タイの料理にかなり近いと思っていいだろう。もともと、ラオスとタイは同系列の民族であるため、食事の内容も似ているのだ。ラオスの主食は米。それも、カオ・ニャオという呼び名のもち米だ。通常、ディップ・カオと呼ばれる竹細工の籠に入って出てくるので覚えておこう。おかずの定番はラープ。肉や魚のバージョンがあり、これに香草やレモン、ライムなどを入れて炒めたもの。鶏肉ならラープ・カイ、牛肉ならラープ・グア、魚ならラープ・パーというように呼び名が変わる。日本ともっとも異なる点は、これらを手で食べること。まず、もち米のカオ・ニャオをひと摘み手にとり、これにラープを合わせてつまむように口に運ぶのがラオスのスタイルとなっている。
また、屋台でよく見かける料理といえば、タム・マークフン。青いパパイヤを細切りにし、野菜と魚のエキスで味付けしたもので、要は炒め物だ。そのほか、ラオスの焼き鳥ピン・カイや魚の塩焼きピン・パーもポピュラーな料理だ。
 ラオスには麺料理も多い。これらは箸を使って食べるが、日本のようにズルズルと音をたてて食べるのは避けよう。代表的な麺料理は米から作る白い麺のフーで、ベトナムでいうフォーのこと。ほかにも、小麦粉で作る黄色い麺のミー、米と片栗粉から作るカオ・ピヤック・セン、素麺のような細いカオ・プンなど種類が多く、メニューも坦々麺風、焼きそば風と多種多様にそろっている。屋台ではインスタントラーメンも食べられるので、散策の途中で小腹を満たすこともできる。
ラオスには麺料理も多い。これらは箸を使って食べるが、日本のようにズルズルと音をたてて食べるのは避けよう。代表的な麺料理は米から作る白い麺のフーで、ベトナムでいうフォーのこと。ほかにも、小麦粉で作る黄色い麺のミー、米と片栗粉から作るカオ・ピヤック・セン、素麺のような細いカオ・プンなど種類が多く、メニューも坦々麺風、焼きそば風と多種多様にそろっている。屋台ではインスタントラーメンも食べられるので、散策の途中で小腹を満たすこともできる。▽ラオス産のお酒とデザート
 フランスが統治していた名残で、フランスパンがおいしいのはベトナムと同様だ。ラオスのサンドイッチは、フランスパンにハムや野菜を挟み、醤油やチリソースで味付けするのが特徴。練乳入りのコーヒーと一緒に、ラオス風の朝食を楽しみたい。
フランスが統治していた名残で、フランスパンがおいしいのはベトナムと同様だ。ラオスのサンドイッチは、フランスパンにハムや野菜を挟み、醤油やチリソースで味付けするのが特徴。練乳入りのコーヒーと一緒に、ラオス風の朝食を楽しみたい。また、ラオスの飲み物といえば、ラオ・ラーオ。沖縄の泡盛のルーツとされる米焼酎のことで、アルコール度数は高いもので40度以上もある。一度も蒸さずにつくるラオ・カーオ、一度蒸して水を加え数日置くラオ・サト、赤米でつくるラオ・カオ・カムの3種類がある。ラオ・ラーオは、ラオス全土で造られており、ツアーによっては酒造りの村へ立ち寄るコースもある。ラオスの国産ビールはビア・ラーオ。ライトビールや黒ビールもあり、乾いた喉を潤すのに最適だ。ちなみに、ビエンチャンの郊外にビア・ラーオ工場があり、予約すれば誰でも製造ラインの見学や試飲ができる。
ラオスの伝統デザートは、クレープ風、ドーナツ風、中華まん風と多彩だが、どことなく全体的に中華風だ。素材はとうもろこし、もち米、バナナ、練乳、ココナッツなど。バナナを焼いただけのクワイ・チーにも一度はトライしたい。ポピュラーなのは、みつまめ風のナム・ワーン。ココナッツミルクに色とりどりの寒天やゼリーが入っていて、ここにタピオカ、黒豆、角切りにしたサツマイモ、パイナップル、パパイヤなどのトッピングを入れて食べる。トッピングによって味が変わるので、毎日食べても飽きがこない一品だ。
▽本場の味なら屋台やマーケットへ
 首都ビエンチャンや観光客の多いルアンパバーンでは、ラオス料理をはじめ、ヨーロッパ料理、和食、中華、タイ料理、ベトナム料理と何でもそろっている。しかし、地元の人々の生活や活気に触れるという意味で、屋台やマーケットへぜひ足を運びたい。ビエンチャンなら、町一番の規模をほこる市場タラート・トンカンカムがお勧め。肉や魚、野菜などの生鮮食品がところ狭しと並ぶなか、屋台スペースでラオスの伝統料理が味わえる。そのほか、近代的な新館もある巨大マーケットのタラート・サオにはフードコート、庶民的な市場タラート・ノントゥアンでは屋台スペースがあり、市内中心部から足を運びやすい。
首都ビエンチャンや観光客の多いルアンパバーンでは、ラオス料理をはじめ、ヨーロッパ料理、和食、中華、タイ料理、ベトナム料理と何でもそろっている。しかし、地元の人々の生活や活気に触れるという意味で、屋台やマーケットへぜひ足を運びたい。ビエンチャンなら、町一番の規模をほこる市場タラート・トンカンカムがお勧め。肉や魚、野菜などの生鮮食品がところ狭しと並ぶなか、屋台スペースでラオスの伝統料理が味わえる。そのほか、近代的な新館もある巨大マーケットのタラート・サオにはフードコート、庶民的な市場タラート・ノントゥアンでは屋台スペースがあり、市内中心部から足を運びやすい。ルアンパバーンなら、ナイトマーケットがいいだろう。国立博物館前のシーサワンウォン通りが歩行者天国になっており、5600メートルの道いっぱいに露天が並ぶにぎわいは地元のパワーを感じる圧巻の風景だ。食べ物の屋台も出ているので、食事目的で訪れても、そぞろ歩きの途中でデザートを楽しんでもいいだろう。

正解:B