取材ノート:アジア大旅行時代、日本の海外旅行市場が生き残るためには
 9月18日に開催されたJATA国際観光会議で、各業界から迎えられた講演者がこの数年著しい成長を遂げているアジア旅行市場の現状と今後の予想、日本市場の展望について語った。中国をはじめとする諸国の成長の現実を捉え、成熟した日本市場を活性化し、新たな旅行需要の創出への糸口を見出すことができるか――。
9月18日に開催されたJATA国際観光会議で、各業界から迎えられた講演者がこの数年著しい成長を遂げているアジア旅行市場の現状と今後の予想、日本市場の展望について語った。中国をはじめとする諸国の成長の現実を捉え、成熟した日本市場を活性化し、新たな旅行需要の創出への糸口を見出すことができるか――。▽デスティネーションとソースマーケットの2面性をもつアジア諸国
太平洋アジア観光協会(PATA)ジョン・コルドフスキ氏は世界観光機関(UNWTO)のデータを用いて、およびアジア各国の現状を伝えた。UNWTOが発表した2008年の海外旅行者数の成長率予測によると、世界平均が前年比3%増から4%増(2007年は6.1%増)であるのに対し、アジア太平洋地域は8%増から10%増(2007年は10.2%増)で、全世界的に成長が減速傾向にあるなかで、アジア太平洋地域はほぼ前年並みの増加が見込まれている。また、アジア諸国はデスティネーションであると同時にソースマーケットであることを指摘し、PATAでは2010年までの3年間、アジアのインバウンドは毎年8%増加し、3億5000万人に達すると予測している。
特に実数では中国、シンガポール、マレーシアの伸びが顕著で、上位10位以内には韓国やタイ、香港も入る。一方で日本人旅行者数の割合は縮小しており、コドルフスキ氏は、交渉力の低下をキーワードに挙げた。アジア諸国の市場が成長するなかで、「デスティネーション側は、減少した日本人旅行者を増加させるよりも、中国などから旅行者を獲得することに注力する」とし、「日本人が望まれていないわけではなく、他に成長の早い市場があるからだということ、そしてデスティネーションとして単一のマーケットが破綻するのを防がなければならないことを理解しなくてはならない」と伝えた。
さらに、コルドフスキ氏は今後、航空会社のM&Aが進むと予想。現在は利益をあげなくとも政府の援助がある安心感から非効率な運営をする航空会社があり、そうした企業は淘汰されていくだろうと述べた。
▽新たな休暇制度の導入で更なる成長が予想される中国海外旅行市場
 中国国際旅行社総社(CITS)副総裁の劉桂香氏によると、中国の海外旅行市場はこの数年、毎年平均で約22%の成長を続けている。2007年には中国政府が認可した渡航先は134ヶ国となり、香港とマカオを含めた海外旅行者数は前年比18.6%増の4095万4000人にのぼった。渡航先としては引き続き、香港、マカオ、ベトナム、韓国、日本など近距離を中心に人気が高かく、日本への訪問者数は20%増の150万人。また、ヨーロッパやアメリカなども伸びてきているという。そして、今年から休暇制度が導入され、2週間の休暇取得が法によって定められた。雇用主の都合により取得できない場合は3倍の給与を支払わなくてはならないとされており、海外旅行市場の拡大も後押しするとみられる。
中国国際旅行社総社(CITS)副総裁の劉桂香氏によると、中国の海外旅行市場はこの数年、毎年平均で約22%の成長を続けている。2007年には中国政府が認可した渡航先は134ヶ国となり、香港とマカオを含めた海外旅行者数は前年比18.6%増の4095万4000人にのぼった。渡航先としては引き続き、香港、マカオ、ベトナム、韓国、日本など近距離を中心に人気が高かく、日本への訪問者数は20%増の150万人。また、ヨーロッパやアメリカなども伸びてきているという。そして、今年から休暇制度が導入され、2週間の休暇取得が法によって定められた。雇用主の都合により取得できない場合は3倍の給与を支払わなくてはならないとされており、海外旅行市場の拡大も後押しするとみられる。2006年の旅行者の構成は女性が54.8%、男性が45.2%で、年齢層では18歳から30歳までが45.9%、31歳から50歳までが35.1%で、若い世代が積極的に海外旅行をしている。また、一世帯あたりの1ヶ月あたりの収入は1万元(約15万5000円)以下が44%で最も多く、1万元以上3万元(約46万5000円)未満が38%。海外旅行をする理由は、「見識を深めたい」(27.9%)、「心身のリラックスのため」(22%)など、経済成長が著しい背景が反映されているという。
旅行形態は周遊型のパッケージ商品の利用が主流で、訪問地の数に比例して見識が広がるという考え方があるようだ。また、移動やビザのコストから一度の旅行で可能な限り多くの土地を訪問したいという意見が多い。一方で、ロングステイやテーマ性の強いツアー、ラグジュアリー商品の需要も富裕層を中心に注目されはじめている。そのほか、MICE市場も堅調に推移している。
現在の課題として、旅行会社間の価格競争、渡航先での中国人旅行者の素行、旅行会社に対する法規制の不完全性などが挙げられる。これに対し、政府は旅行関連の法制度の整備などに努めており、少しずつ健全な市場へと変化してきているという。
▽日本市場の仕入環境の変化と今後の展望
 こうした環境において、中国国内の欧米系4ツ星から5ツ星のホテルは送客数に応じて国籍ごとに料金を設定しており、中国市場が最安値とは限らない状況にも関わらず、中国人の利用占有率は大幅に拡大している。その一方で、日本人海外旅行市場は旅行者数の伸び悩みによる仕入ボリュームの減少、間際販売や直販の拡大などにより、中国における日本市場のプライオリティは低下し、仕入交渉が難しくなっていくと予想されるという。これは中国にのみいえることではない。JTB CHINA董事長の吉村久夫氏は今後の仕入戦略について、(1)仕入先の選択と集中(2)実績を残した上での仕入れ交渉(3)オフシーズンへの送客協力などサプライヤーへのメリット提供(4)日本以外の旅行会社との共同仕入の4つを立て「グローバルマーケットの動向を常に意識し、地域にあった仕入戦略の構築が大切」と述べた。
こうした環境において、中国国内の欧米系4ツ星から5ツ星のホテルは送客数に応じて国籍ごとに料金を設定しており、中国市場が最安値とは限らない状況にも関わらず、中国人の利用占有率は大幅に拡大している。その一方で、日本人海外旅行市場は旅行者数の伸び悩みによる仕入ボリュームの減少、間際販売や直販の拡大などにより、中国における日本市場のプライオリティは低下し、仕入交渉が難しくなっていくと予想されるという。これは中国にのみいえることではない。JTB CHINA董事長の吉村久夫氏は今後の仕入戦略について、(1)仕入先の選択と集中(2)実績を残した上での仕入れ交渉(3)オフシーズンへの送客協力などサプライヤーへのメリット提供(4)日本以外の旅行会社との共同仕入の4つを立て「グローバルマーケットの動向を常に意識し、地域にあった仕入戦略の構築が大切」と述べた。▽日中韓の連携で相乗効果をはかり、海外旅行市場の活性化を
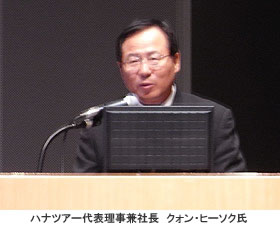 もうひとつの成長市場である韓国は、1995年から2007年までの間、平均で年10%の成長を遂げている。旅行者はシニア層と女性層がメインで、特に個人旅行の需要が拡大。今年は燃油価格の高騰などの影響で状況は厳しく微減するのではないかとの見方もあるが、2010年までの3年間で13%の成長が予想されている。2007年の渡航先は中国が477万7000人(35.8%)、日本が260万1000人(19.5%)とこの2国で55.3%を占め近距離のデスティネーションが好まれていることがわかる。
もうひとつの成長市場である韓国は、1995年から2007年までの間、平均で年10%の成長を遂げている。旅行者はシニア層と女性層がメインで、特に個人旅行の需要が拡大。今年は燃油価格の高騰などの影響で状況は厳しく微減するのではないかとの見方もあるが、2010年までの3年間で13%の成長が予想されている。2007年の渡航先は中国が477万7000人(35.8%)、日本が260万1000人(19.5%)とこの2国で55.3%を占め近距離のデスティネーションが好まれていることがわかる。ハナツアー代表理事兼社長のクォン・ヒーソク氏は「日本、中国、韓国の3国が連携して相乗効果をはかることが大切だ」と言及。今後の展望として、オープンスカイ政策によるLCCビジネスの拡大で旅行費用が減少し、燃油価格の高騰により近距離旅行が増加する。日本と韓国の高齢化で余暇が拡大し、アウトバウンド市場はさらに伸びるとした。
▽コンチネンタル航空の中国、インド、日本における戦略
 来年のスターアライアンスへの加盟を予定するコンチネンタル航空(CO)は95年以降、ヒューストンをハブにネットワークを拡大し、運航する都市は国内外のバランス重視し、改善に成功した。機材を比較的小型の3種類に限定しコストを削減、様々な路線に柔軟に対応できるようにし、日本をはじめアジアの都市にも数多く就航している。
来年のスターアライアンスへの加盟を予定するコンチネンタル航空(CO)は95年以降、ヒューストンをハブにネットワークを拡大し、運航する都市は国内外のバランス重視し、改善に成功した。機材を比較的小型の3種類に限定しコストを削減、様々な路線に柔軟に対応できるようにし、日本をはじめアジアの都市にも数多く就航している。中国はビジネスとレジャーの双方でアメリカへの需要が高く、10日間で多くの都市を周遊する30年前の日本の旅行スタイルと同じ傾向がみられる。太平洋路線はニューヨークにベースとする戦略で、この10年間で中国/ニューヨーク間の市場は2.5倍に拡大した。成田、北京、上海で比較すると、依然として成田が圧倒的に供給量は多いが、2003年のSARS以降は北京がとくに伸びている。CO日本支社長のチャールズ・ダンカン氏は「今後もニューヨークをハブにしながら、中国でグアム線を開設したい」と語る。インドでは、05年11月にニューデリーに、07年10月にムンバイにそれぞれ直行便を就航。毎日1200人をインドからニューヨークに運んでおり、直行便の需要は現在も拡大しているという。
現在COは、ロタ島へのチャーター便やビジネスクラス商品などターゲットを絞り特化した商品と品質へのこだわりが奏功しているとみている。今後も、ニューヨーク、南米、ミクロネシアの3路線に重点をおいて展開する方針だ。またダンカン氏は、2010年の首都圏空港発着枠の拡大の際に、成田の集客力を失わないためには空港へのアクセス改善が必要と言及した。具体的な例として日本橋から30分で行けるように、とした。さらにLCCについてはマーケットへの参入により競争力が求められるようになり、全体が活性化すると前向きな姿勢を示し、LCCは機材の老朽化などの要因から相対的にみてそれほどローコストではなくなりつつあるのではないかとの見解を示した。
中国を中心にアジアの海外旅行市場は今後も拡大する見通しで、その影響を受け、成熟した日本市場の価値が低下してきている。しかし、これは新たな商機を生み出す機会でもある。この機会を上手く捉え、他国を意識し、競争だけではなく協力の姿勢で、これまでとは異なるビジネスモデルを構築しなければならない。



