海外教育旅行は生徒の主体性と安全の両立がカギ、将来につながる仕組み作りも-シンポジウム開催
「学生の主体性」「将来につなげる教育旅行」をテーマにパネルディスカッション
 |  |
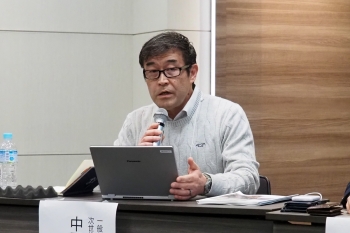 次世代教育ネットワーキング機構理事・事務局長の中野憲氏
次世代教育ネットワーキング機構理事・事務局長の中野憲氏
第2部のパネルディスカッションでは中野氏の司会のもと、2つのテーマで議論した。1つ目のテーマは「生徒の主体性をどのように海外教育旅行に取り込むか」。宍戸氏は「生徒たちが自分たちで考えて動くことをプログラムに入れなければならない」と生徒が主体的に動けるよう企画することが重要であるとした。その一方で、「海外旅行は安全面の問題がある」と改めて課題を指摘した。
城川氏も、海外教育旅行先としてアジアを選ぶ場合について「保護者から心配されるのが安心、安全、病気や清潔感」と説明。「過保護感が高まるなか、保護者に納得感を持たせるものを企画するのが苦労する」と現場の視点で話し、「(主体性との)バランスをどうやってとるかが今後大切になる」と話した。
 文部科学省官民協働海外留学創出プロジェクト広報・マーケティングチームリーダーの西川朋子氏
文部科学省官民協働海外留学創出プロジェクト広報・マーケティングチームリーダーの西川朋子氏
このほか、加藤氏は「今も昔も変わらないのは、海外研修に行った生徒のモチベーションが上がり、高い目標を掲げるようになるケースは、向こうで友達ができたとき。海外の人と共感する体験が大きい」とコメント。「(プログラムで)そうなる確率をいかに高めていくか」が重要であるとした。
2つ目のテーマはグローバル人材の育成の観点から「中高時代に体験した海外教育旅行をその後のキャリアにどうつなげるか」。これに対し、西川氏は「同質性が強い日本を飛び出すからこそ得られる問題意識の種を得て、悩み、課題意識の小さな種と友達が得られる海外研修なら、必ず次につながる」と訴えた。
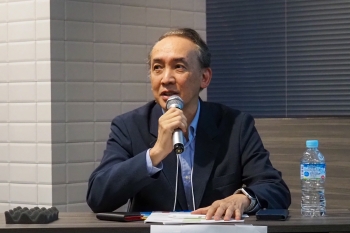 海外留学協議会事務局長の星野達彦氏
海外留学協議会事務局長の星野達彦氏
星野氏は、海外教育旅行に参加した生徒で、直後は意欲的になるものの、受験や進学などによりいつもの日常に戻ってしまうことがあると指摘。体験を将来につなげるため、学校側に留学進路を指導できる資格者や、教師や先輩など生徒の身近な人間が相談に応じられるような体制を作ることを提案した。加えて同氏は「去年体験した人がまだ熱いうちに次の世代に話をする機会を作るといった努力が必要では」と、先を見据えた行動も必要とした。
宍戸氏は「日本企業が弱体化しており、学生は『どう活躍できるか』が日本では見えない」と指摘。「家族旅行や中学、高校など、ライフプランの中で教育の経験がどうつながるかをしっかり議論すべき」と話した。
 昌平中学校・高等学校学園長の城川雅士氏
昌平中学校・高等学校学園長の城川雅士氏
城川氏は「生徒たちには海外で体験したことをいかに日本の将来につなげるかが最終テーマと話している」と説明。一方で「実際の中高生を見ると、企画と現実的なギャップは感じざるを得ない」とし、「プログラムで本質的な海外との違いをどれだけ感じさせるか」が重要であるとした。
また、加藤氏は実施側の学校の教員たちの教育の必要性を指摘。宍戸氏も、英語教師など限られた教師しか参加せず、仕事がたまるから海外研修に行きたがらない教師もいるとして「先生たちが変わらないとよくならない。先生たちの意識教育は重要」と訴えた。