取材ノート:国が本腰入れるMICE、認知浸透と人材育成が急務
 第1回の「MICE推進協議会」が2009年12月17日に開催され、MICE関連団体などの長からなるメンバーと関係省庁が集まった。「MICEの参加者は主導的な人が多く、よい印象を持つと口コミで広がる効果もある。日本の認知度向上にとって大変重要」と国際観光振興機構(JNTO)理事長の間宮忠敏氏が、観光面での直接的なメリットを提示したほか、日本経済団体連合会観光委員の太田誠氏は「観光は日本のよさを理解してもらえる文化的な安全保障につながる。将来、資源と人材が必要となる日本にとって、MICEで人を集める方向性は産業界にとって重要」と、産業界の立場からMICEを語った。それぞれの立場から発せられた意見から、MICE推進の課題やめざす方向性がうかがえた。
第1回の「MICE推進協議会」が2009年12月17日に開催され、MICE関連団体などの長からなるメンバーと関係省庁が集まった。「MICEの参加者は主導的な人が多く、よい印象を持つと口コミで広がる効果もある。日本の認知度向上にとって大変重要」と国際観光振興機構(JNTO)理事長の間宮忠敏氏が、観光面での直接的なメリットを提示したほか、日本経済団体連合会観光委員の太田誠氏は「観光は日本のよさを理解してもらえる文化的な安全保障につながる。将来、資源と人材が必要となる日本にとって、MICEで人を集める方向性は産業界にとって重要」と、産業界の立場からMICEを語った。それぞれの立場から発せられた意見から、MICE推進の課題やめざす方向性がうかがえた。MICEの読み方と意味がまだ浸透していない
 政府は2010年をMICEイヤーと位置づけ、これまでの国際会議だけでなくMICE全体を推進する方針だが、そのためには国内ではMICEという言葉の認知、海外では日本がMICEにふさわしい場所であることを知ってもらわなければならない。
政府は2010年をMICEイヤーと位置づけ、これまでの国際会議だけでなくMICE全体を推進する方針だが、そのためには国内ではMICEという言葉の認知、海外では日本がMICEにふさわしい場所であることを知ってもらわなければならない。今回の会議でもMICEの4分野にわたって重要な課題とされたのが、国民に対するMICEという言葉とその概念の周知だ。JNTOの間宮氏は、「2009年12月に開催された国際ミーティング・エキスポ(IME)で各地のコンベンションビューローなどにアンケートを取ったところ、MICEのうちCへの取り組みは100%だがMとIは半分、Eは2割くらいしか取り組んでいない。知名度の向上と、C以外の取り組みを増やさなくてはいけない」と現状改善を強く求めた。日本コンベンション&コングレスビューロー(JCCB)会長の猪口邦子氏は「まだ一般の人はMICEという言葉の読み方も意味もわからない。読み方や、それぞれの文字の意味も書いて示すべき」と指摘し、さらに「日本は一般観光が世界28位に対し、国際会議誘致は4位。国際会議が日本の隠れた実力分野であることを国民に理解されるような広報活動を」と強調した。
外国へのプロモーションについて、日本ホテル協会会長中村裕氏は「MICEビジネスは国と国の競争。日本は他の国と比べ何が強いのかを打ち出すことが大事だ。他の国にはないユニークベニューでのテーマパーティなど、日本的な催しを打ち出す必要がある」と話す。
MICE誘致に関し、観光庁審議官の甲斐正彰氏は、「来年度は海外の有名見本市で、日本がMICEを誘致する場を設ける。さらにこれまで国際会議ではキーパーソンを招聘したり、総理大臣の名前で誘致をしたりしていたが、MICE誘致でも同じようにやっていきたい」と説明している。
受け入れ態勢の課題
 さらに、多くの人が指摘したのがビザの問題だ。日本商工会議所観光専門委員会委員長の須田寛氏は「大型団体の入出国手続きの円滑化など、特別な審査を講じてもらえるとよい」と話し、経団連の太田氏も「多忙なモスクワのビジネスマンに、2日から3日間の滞在に必要な書類を1ヶ月も前に出させるのは難しい」と過去の事例で課題を示した。これに対し、外務省広報文化交流部長の門司健次郎氏は「関係省庁で連携して取り組んでいきたい」と応じ、観光庁の甲斐氏は、観光立国推進本部の外客誘致ワーキングチームで中国のビザ発給の緩和に向けた取り組みをしていることを紹介した。
さらに、多くの人が指摘したのがビザの問題だ。日本商工会議所観光専門委員会委員長の須田寛氏は「大型団体の入出国手続きの円滑化など、特別な審査を講じてもらえるとよい」と話し、経団連の太田氏も「多忙なモスクワのビジネスマンに、2日から3日間の滞在に必要な書類を1ヶ月も前に出させるのは難しい」と過去の事例で課題を示した。これに対し、外務省広報文化交流部長の門司健次郎氏は「関係省庁で連携して取り組んでいきたい」と応じ、観光庁の甲斐氏は、観光立国推進本部の外客誘致ワーキングチームで中国のビザ発給の緩和に向けた取り組みをしていることを紹介した。施設インフラなどハード面の課題もある。特に、インセンティブで問題になるのが、ユニークベニューの使いにくさだ。日本旅行業協会(JATA)会長の金井耿氏は「外国では、美術館、博物館、城などがMICEのレセプションで使える。ウィーンのミーティングプランナーズガイドでは公的施設のMICE用施設を掲載しており、ウィーン自然史博物館ではスペース、収容人数を提示している」と事例を紹介し、「日本では美術館、博物館は使用の手続きが煩雑で直前にならないと予約できない。何年も前から予約できないとMICEとして招致しにくい」と公的施設の使用条件の緩和を訴えた。これに対し、観光庁参事官の大滝昌平氏は「ユニークベニューとして解放している施設のリストを作ろうとしている。制度的な問題が出てくれば、関係省庁などに協力を求めていきたい」と、観光庁の取り組みを説明した。
一方、存在自体がユニークといえる旅館は、欧米の会社の30人から40人単位のインセンティブに利用されているという。「畳に座ってお膳を前に日本酒を豪快に楽しむスタイルなどは、非常に満足度が高い。GDSを活用した予約システムを構築し、情報発信しながら予約を積極的に受けていく」と国際観光旅館連盟会長佐藤義正氏は話す。ただし、「外国のキャッシュカードが使えるATMがない。たまたまセブン銀行のATMでキャッシングしてもらったが、国際会議で地方都市に誘致するとATM設備も必要になる」と課題も加える。
このほか、商工会議所の須田氏から「地方の展示場、会議場は十分でない。立派なビルである必要はないので、有休施設を使うなどコストのかからない方法で整備をしてほしい」と、地方の実態について指摘があった。
経験やノウハウを有するMICE人材育成を
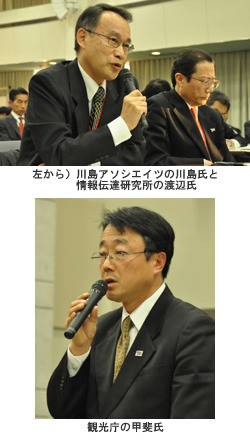 経験やノウハウを持ったMICEの人材育成についても、「試験が難しく通訳者が足りない。国際会議の企画者が育っていない」といった、さまざまな指摘があった。JCCBの猪口氏は「この分野全体の人材の評価を高めていくことが重要。観光教育も大事」と話す。また、JNTO間宮氏は「コンベンションビューローもMICE専門の人材が増えていない。誘致の仕方、資金調達、スポンサーシップのアレンジの仕方、設営のノウハウなどのインターナショナルスタンダードを持つ人の養成が急務」という。
経験やノウハウを持ったMICEの人材育成についても、「試験が難しく通訳者が足りない。国際会議の企画者が育っていない」といった、さまざまな指摘があった。JCCBの猪口氏は「この分野全体の人材の評価を高めていくことが重要。観光教育も大事」と話す。また、JNTO間宮氏は「コンベンションビューローもMICE専門の人材が増えていない。誘致の仕方、資金調達、スポンサーシップのアレンジの仕方、設営のノウハウなどのインターナショナルスタンダードを持つ人の養成が急務」という。同会議ではMICE分野からYOKOSO!JAPAN大使に任命された、国際会議運営の専門家である川島アソシエイツ代表の川島久男氏と、情報伝達研究所代表取締役の渡辺厚氏も出席。この問題について川島氏は「会議の国際本部は“日本で開催する真のメリット”を知りたがっているが、日本の国際会議主催者や業界はそれを把握していない。反対に国際本部も日本の業界を知り得ていないというミスギャップがある」と指摘した上で、「海外の有力PCO(プロフェッショナル・コングレス・オーガナイザー)とコンベンションビューローは交流があり、インターンを受け入れている。そこに日本の業界の人が研修に行くのもいいのではないか」と提案。
ベニューの立場で30年間コンベンションを受け入れてきたという渡辺氏は「国内では観光分野で先駆的な立教大学観光学部でも、コンベンションやMICEの講座は1つしかない。韓国を含め諸外国の大学はコンベンションの学科、講座が多岐に渡っている。高等教育機関での人材育成を期待したい」と話した。
これらの意見をふまえ、観光庁の甲斐氏は「ここで出た課題は、観光庁だけでなく横断的なしくみを活用しながら考えていきたい」とし、「ビジット・ジャパン・キャンペーンも2003年にはじめ、6年かけて浸透してきた。MICEは行政として本格的に取り組んで間もない分野。大きく成長させていきたい」と結んだ。
▽関連記事
◆観光庁、MICE推進協議会開催、公的施設の使用条件の緩和要望も(2009/12/21)
◆10年度観光予算案、2倍の126.5億円−訪日事業が3倍、受入整備は約5倍に(2010/01/25)
取材:平山喜代江