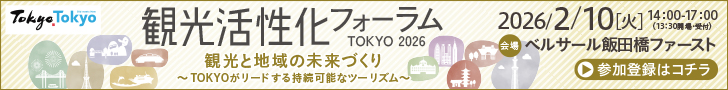JATA古木副会長、IATA運賃などは「独禁法を適用すべき」−国交省懇談会で
日本旅行業協会(JATA)副会長の古木康太郎氏は12月4日、第4回「国際航空に関する独占禁止法適用除外制度のあり方に関する懇談会」で、IATA運賃協定とキャリア運賃協定、IATA代理店協定について、独占禁止法の適用除外は「廃止すべき」との意見を述べた。同懇談会は公正取引委員会が2007年11月にまとめた報告書を受けて開催しているもので、4日はJATA、航空貨物運送協会、日本荷主協会、公正取引委員会の4者からヒアリングを実施した。
古木氏は、「国際航空運送協会(IATA)が設立されてからの63年間、我々の業界に大きな貢献をしたのは事実」としつつ、「JATAの基本的考え方として、現在のIATA運賃協定は事実上形骸化しているうえ、弾力的な運賃設定を阻害しており、独禁法の適用の対象とすべき」と言及。ただし、インターラインなど利用者の利便性を実現する有益な航空会社間合意は維持する必要があると付言した。キャリア運賃については、「申請された運賃とかけ離れており、有名無実化した意味のない運賃」と説明し、独禁法の適用を訴えた。また、フレックスフェアについては、「日本が取り入れる場合は、欧米と同じような土俵に乗ることが望ましい」としつつ、「競争力に欠ける高い運賃で、毎年上昇することが危惧される」と疑問を示し、こうした疑問点については「今後も意見を述べていきたい」と語った。
さらに、IATA運賃協定が独禁法の適用を受けた場合、「アライアンス運賃がそれに代わる運賃協定となる」と予測。「アライアンス運賃全てが悪いと言うわけではなく、利用者にとって非常に利便性の高いものも考えられる」としつつ、「主要3アライアンスで市場独占率は70%以上。今後の提携規模やネットワークの拡大により、市場支配的かつ排他的状況が生まれる可能性もある」と説明。その上で、「日系航空会社がアライアンスの他の航空会社と運賃などの協定を締結する場合も、独禁法の適用対象にできる余地を残しておくべきではないか」と語った。
また、IATA代理店協定については、「IATA側の一方的な規制が強く、加盟代理店は過剰な負担を受け、財務的、営業的に大きな制約を受けている」とし、精算回数の月4回への変更、「SAME DAY VOID」の導入などを例示した。
▽貨物では適用除外廃止で事務作業が煩雑化−公取は「必要性とぼしい」
その他のヒアリング出席団体では、航空貨物輸送協会が、すでに適用除外が廃止となったヨーロッパやオーストラリアの路線で「運賃を航空会社ごと、路線ごとに正確に管理するなど、事務が著しく煩雑化し、迅速かつ正確な実務の実行に支障をきたしている」ことから反対意見を述べたが、日本荷主協会は独禁法適用に賛意を表した。
公正取引委員会からは、「IATA運賃協定を適用除外としておく必要性はとぼしい」と改めて説明。この理由として、インターラインはIATA運賃協定への適用除外が失効した地域でも引き続き実施されていることや、航空会社が必ずしもIATA運賃全額を収受していないこと、キャリア運賃改定の際の指標として機能していることなどを挙げた。インターラインについて発表者の公正取引委員会経済取引局調整課長の東出浩一氏は、「運賃である必要があるのか」と疑問を述べ、仕組みとして実現できるのではないか、との意見を述べた。また、キャリア運賃協定、コードシェア協定、マイレージ協定については、適用除外制度の対象としなくても実施可能と主張した。
なお、懇談会では、これまでの議論を踏まえ、2009年2月5日に第5回懇談会を開催し報告書の素案を検討、3月5日の第6回懇談会で報告書のとりまとめを実施する予定だ。
▽関連記事
◆大韓航空、「自由な運賃設定が望ましい」−独禁法適用除外制度の懇談会で(2008.11.14)
◆IATA運賃の「規則」重要−独禁法適用除外見直しで日系2社、政策的観点にも言及(2008.10.31)
◆鈴木航空局長、適用除外議論「公取は現在でも対応できる」−下限撤廃も準備(2007.10.09)
◆公取委、国際航空協定に関する独禁法のあり方のパブリックコメント開始(2007.10.02)
◆国際航空協定は独禁法適用の方向−公取の報告書素案「抜本的見直しを」(2007.09.21)
◆IATA運賃の独禁法適用、規制研の議論受け報告書作成へ(2007.07.20)
◆独禁法適用除外、JATAは見直しに賛成−インターラインなど一部で代替を(2007.06.11)
◆航空運賃の独禁法適用除外、焦点はインターライニング−IATAなどが強調(2007.05.28)
◆鈴木航空局長、IATA運賃に一定の理解示す−酒類没収も対応策を(2007.03.05)
古木氏は、「国際航空運送協会(IATA)が設立されてからの63年間、我々の業界に大きな貢献をしたのは事実」としつつ、「JATAの基本的考え方として、現在のIATA運賃協定は事実上形骸化しているうえ、弾力的な運賃設定を阻害しており、独禁法の適用の対象とすべき」と言及。ただし、インターラインなど利用者の利便性を実現する有益な航空会社間合意は維持する必要があると付言した。キャリア運賃については、「申請された運賃とかけ離れており、有名無実化した意味のない運賃」と説明し、独禁法の適用を訴えた。また、フレックスフェアについては、「日本が取り入れる場合は、欧米と同じような土俵に乗ることが望ましい」としつつ、「競争力に欠ける高い運賃で、毎年上昇することが危惧される」と疑問を示し、こうした疑問点については「今後も意見を述べていきたい」と語った。
さらに、IATA運賃協定が独禁法の適用を受けた場合、「アライアンス運賃がそれに代わる運賃協定となる」と予測。「アライアンス運賃全てが悪いと言うわけではなく、利用者にとって非常に利便性の高いものも考えられる」としつつ、「主要3アライアンスで市場独占率は70%以上。今後の提携規模やネットワークの拡大により、市場支配的かつ排他的状況が生まれる可能性もある」と説明。その上で、「日系航空会社がアライアンスの他の航空会社と運賃などの協定を締結する場合も、独禁法の適用対象にできる余地を残しておくべきではないか」と語った。
また、IATA代理店協定については、「IATA側の一方的な規制が強く、加盟代理店は過剰な負担を受け、財務的、営業的に大きな制約を受けている」とし、精算回数の月4回への変更、「SAME DAY VOID」の導入などを例示した。
▽貨物では適用除外廃止で事務作業が煩雑化−公取は「必要性とぼしい」
その他のヒアリング出席団体では、航空貨物輸送協会が、すでに適用除外が廃止となったヨーロッパやオーストラリアの路線で「運賃を航空会社ごと、路線ごとに正確に管理するなど、事務が著しく煩雑化し、迅速かつ正確な実務の実行に支障をきたしている」ことから反対意見を述べたが、日本荷主協会は独禁法適用に賛意を表した。
公正取引委員会からは、「IATA運賃協定を適用除外としておく必要性はとぼしい」と改めて説明。この理由として、インターラインはIATA運賃協定への適用除外が失効した地域でも引き続き実施されていることや、航空会社が必ずしもIATA運賃全額を収受していないこと、キャリア運賃改定の際の指標として機能していることなどを挙げた。インターラインについて発表者の公正取引委員会経済取引局調整課長の東出浩一氏は、「運賃である必要があるのか」と疑問を述べ、仕組みとして実現できるのではないか、との意見を述べた。また、キャリア運賃協定、コードシェア協定、マイレージ協定については、適用除外制度の対象としなくても実施可能と主張した。
なお、懇談会では、これまでの議論を踏まえ、2009年2月5日に第5回懇談会を開催し報告書の素案を検討、3月5日の第6回懇談会で報告書のとりまとめを実施する予定だ。
▽関連記事
◆大韓航空、「自由な運賃設定が望ましい」−独禁法適用除外制度の懇談会で(2008.11.14)
◆IATA運賃の「規則」重要−独禁法適用除外見直しで日系2社、政策的観点にも言及(2008.10.31)
◆鈴木航空局長、適用除外議論「公取は現在でも対応できる」−下限撤廃も準備(2007.10.09)
◆公取委、国際航空協定に関する独禁法のあり方のパブリックコメント開始(2007.10.02)
◆国際航空協定は独禁法適用の方向−公取の報告書素案「抜本的見直しを」(2007.09.21)
◆IATA運賃の独禁法適用、規制研の議論受け報告書作成へ(2007.07.20)
◆独禁法適用除外、JATAは見直しに賛成−インターラインなど一部で代替を(2007.06.11)
◆航空運賃の独禁法適用除外、焦点はインターライニング−IATAなどが強調(2007.05.28)
◆鈴木航空局長、IATA運賃に一定の理解示す−酒類没収も対応策を(2007.03.05)