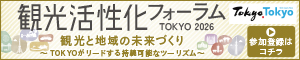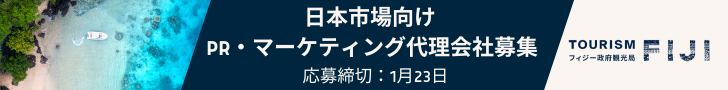適用除外制度、運賃・コードシェア協定など個別の協定を重視しつつ議論へ
 国土交通省航空局は8月28日、国際航空に関する独占禁止法適用除外制度のあり方に関する懇談会を開催、航空局長の前田隆平氏は冒頭の挨拶で、「欧米の流れを受けた公正取引委員会の結論があるが、企業間提携もあらゆる形で有効に活用され、成田や羽田の国際線拡充など、まさにタイムリー、重要なテーマになる」と、深みのある議論を出席した委員に要望した。座長を務める一橋大学大学院の山内弘隆氏は「(公取では)激しい議論の結果、見直しという結論を得た。航空分野以外の客観的な議論であったが、航空分野の政策、独特のものを含めた相対関係のなかで議論し、方向性を見いだしたい」と挨拶し、年度内に意見をまとめる考えだ。
国土交通省航空局は8月28日、国際航空に関する独占禁止法適用除外制度のあり方に関する懇談会を開催、航空局長の前田隆平氏は冒頭の挨拶で、「欧米の流れを受けた公正取引委員会の結論があるが、企業間提携もあらゆる形で有効に活用され、成田や羽田の国際線拡充など、まさにタイムリー、重要なテーマになる」と、深みのある議論を出席した委員に要望した。座長を務める一橋大学大学院の山内弘隆氏は「(公取では)激しい議論の結果、見直しという結論を得た。航空分野以外の客観的な議論であったが、航空分野の政策、独特のものを含めた相対関係のなかで議論し、方向性を見いだしたい」と挨拶し、年度内に意見をまとめる考えだ。今回の会合は現状と課題を整理。国際航空に関する航空運送事業者間の協定には、IATA運賃協定、キャリア運賃協定の運賃協定をはじめ、コードシェア協定、シベリア上空通過などを含むプール協定、連絡運輸に関する協定、代理店規則、サービス会議規則、FFP協定があり、昨年度は旅客231件、貨物53件が適用除外として認可を受けた件数。適用除外を規定する根拠として、航空法が制定された1952年以降、1997年に個別のカルテルを見直す動きから改正、1999年に公正取引委員会の関与を規定するなど、制度、運用を変更してきているところ。
課題としては公取の抜本的な見直しの意見もあるが、政府の規制改革推進の答申などにおいて、「適用除外制度については、連帯運送が可能となるよう配慮した上で、廃止すべき」、「アライアンス内での協同化の促進を認めつつ、アライアンス間競争をより一層促進するべく、国際航空輸送に対する独占禁止法の弾力的な適用が行われる必要がある」との見解もあり、国際情勢の変化にもあわせた議論が要請されている。この懇談会ではアジア各国での独禁法(競争法)の運用状況と航空の自由化、アライアンスの進展などとともに競争政策上の要請と航空政策のバランスを保ちつつ、議論を深めていく。なお、次回の懇談会は10月30日に予定、航空会社からのヒアリングを行う。