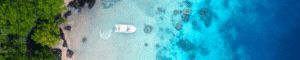取材ノート: エア・タヒチ・ヌイと立教大学にみる、産学連携の効果と課題
エア・タヒチ・ヌイと立教大学にみる、産学連携の効果と課題
〜新鮮な視点と機動力で生まれた、タヒチ・スケッチ・ツアー〜
 エア・タヒチ・ヌイ(TN)と立教大学の庄司准教授ゼミナールでは、2006年からインターンシップを開始。この作業中の会話から企画の提案が持ち上がり、正式に庄司ゼミでの研究テーマに「新しいセグメント(顧客層)へのタヒチ旅行」が取り上げられた。課題は(1)TNの搭乗客を増やすこと、(2)パペーテを売ること、の2つ。これにより生まれた今回の企画「スケッチ・ツアー」は、学生の発想と機動力に業界の経験が合致した成功例といえる。企画内容に対する実地調査に同行し、そこで垣間見た産学連携の効果と今後の課題をレポートする。
エア・タヒチ・ヌイ(TN)と立教大学の庄司准教授ゼミナールでは、2006年からインターンシップを開始。この作業中の会話から企画の提案が持ち上がり、正式に庄司ゼミでの研究テーマに「新しいセグメント(顧客層)へのタヒチ旅行」が取り上げられた。課題は(1)TNの搭乗客を増やすこと、(2)パペーテを売ること、の2つ。これにより生まれた今回の企画「スケッチ・ツアー」は、学生の発想と機動力に業界の経験が合致した成功例といえる。企画内容に対する実地調査に同行し、そこで垣間見た産学連携の効果と今後の課題をレポートする。
(取材協力:・エア・タヒチ・ヌイ、タヒチ観光局、メリディアン・タヒチ、シェラトン・モーレア・ラグーン・リゾート&スパ)
▽関連記事
◆現地レポート−タヒチ スケッチ・ツアーを皮切りに、シニア向け素材に注目(2008/03/27)
◆フォトニュース−タヒチ、シニアの絵心を刺激する景色と雰囲気にあふれた島々(2008/03/28)
身近な話題から課題を提供、モチベーション向上
 きっかけは、ゼミ生の渡辺菜穂さんがインターンシップをしていた当時、話題のテレビドラマ「電車男」の特別編がタヒチで撮影されることから、TNマーケティング本部長の柳川悦子氏に「このドラマがタヒチのプロモーションになると思うか」と聞かれたこと。渡辺さんは「テレビに露出することで何かしら効果になると思う。ただ、時間とお金がないと難しいし、もう一つ何かがないとタヒチにまで行こうと思わないのでは」と意見を述べたところ、「それが何か、考えて欲しい」と課題が与えられた。そこで06年度の終わりごろ、ゼミの研究課題に設定。渡辺さんとゼミ生の正木賢輔さん、直井廉東さんは企画に乗り出した。「まさか学生に企画を任せくれるなんて」と、モチベーションが高まったという。
きっかけは、ゼミ生の渡辺菜穂さんがインターンシップをしていた当時、話題のテレビドラマ「電車男」の特別編がタヒチで撮影されることから、TNマーケティング本部長の柳川悦子氏に「このドラマがタヒチのプロモーションになると思うか」と聞かれたこと。渡辺さんは「テレビに露出することで何かしら効果になると思う。ただ、時間とお金がないと難しいし、もう一つ何かがないとタヒチにまで行こうと思わないのでは」と意見を述べたところ、「それが何か、考えて欲しい」と課題が与えられた。そこで06年度の終わりごろ、ゼミの研究課題に設定。渡辺さんとゼミ生の正木賢輔さん、直井廉東さんは企画に乗り出した。「まさか学生に企画を任せくれるなんて」と、モチベーションが高まったという。
単価30万円から40万円の60万人市場、データで有用性を証明
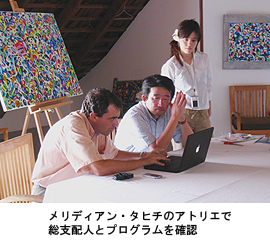 消費者調査では「高額で行けないけど、いつか行きたい」との声が多い一方で、タヒチで何ができるか、どこにあるのかさえ知られていないことが判明。ターゲットをリタイアしたシニアとし、具体的なタヒチ旅行の切り口を探しはじめた。また、シニアから「仕事や子育てを終えて生きがいになることをしたいけれど、自分が今、何をしたいのか分からず、淋しくなるときがある」という答えが多いことも印象的だった。そこで注目したのが、画家・ポール・ゴーギャン。「ゴーギャンが第2の人生を始めたこの地でのんびり考えれば、生活に追われて忘れていた自分を取り戻すきっかけになるのでは」と思いついた。
消費者調査では「高額で行けないけど、いつか行きたい」との声が多い一方で、タヒチで何ができるか、どこにあるのかさえ知られていないことが判明。ターゲットをリタイアしたシニアとし、具体的なタヒチ旅行の切り口を探しはじめた。また、シニアから「仕事や子育てを終えて生きがいになることをしたいけれど、自分が今、何をしたいのか分からず、淋しくなるときがある」という答えが多いことも印象的だった。そこで注目したのが、画家・ポール・ゴーギャン。「ゴーギャンが第2の人生を始めたこの地でのんびり考えれば、生活に追われて忘れていた自分を取り戻すきっかけになるのでは」と思いついた。
その時、庄司准教授に「日本人には何もしない旅行は難しい」という話を聞き、ゴーギャンの「絵」に目を向けた。自分で描く喜びだけでなく、制作に時間を使うこともポイントだ。調べてみるとシニアの絵画愛好家が約60万人の市場であることが推察できた。そこで、07年7月のプレゼンでは「その1%でも6000人。30万円から40万円の単価ならインパクトある」と強調。切り口とデータ証明がTNの目に留まり、本格的に企画化に向けて動くことになった。渡辺さんはプレゼンについて「(TNの)日本支社長まで同席してくれたことに感激した」と言う。企業側の真摯な態度が、学生の本気度をさらに動かすといえるだろう。
現場の大切さ学ぶ場に
 正木さんは「企画段階では、エア・タヒチ・ヌイさんは突拍子もない発想を期待していると思い、気が楽だった。でも、具体化に向けて走り出すと、航空会社ホテルなど、1つの商品を作るのに、いろいろな人が関わって、調整しながら動いていることを知った。これはゼミの研究だけでは分からなかったこと」と実感を語る。
正木さんは「企画段階では、エア・タヒチ・ヌイさんは突拍子もない発想を期待していると思い、気が楽だった。でも、具体化に向けて走り出すと、航空会社ホテルなど、1つの商品を作るのに、いろいろな人が関わって、調整しながら動いていることを知った。これはゼミの研究だけでは分からなかったこと」と実感を語る。
実地調査でも学んだ点が多かった。同行したプレスツアーの参加者に企画のターゲットと同年代の参加者がいたが、視察であちこち巡るうち、かなり疲労していた。それを見た直井さんは「この日程のままではお客様は満足しない。現場を自分の足で回ることは大切」と感じたという。渡辺さんは「滞在先からスケッチポイントまでは思った以上に距離があり、個人旅行者が自分で行くのは難しい。手配が課題になると思う」としながらも、「タヒチの生活を見て日本人と価値観が違うことを感じ、いろんな生き方があることに気付いた。ツアーを通してそんな面も感じてもらえれば、大きな財産を提供できるのでは」と、課題とともに企画のもつ新たな魅力に気付いたようだ。
互いの強みと得意分野で弱点を補完し、業務の幅を拡充
 インターンシップで学生の実務を担当し、今回の実地調査にも同行したTN旅客営業部の中村真樹さんは今回の協同同企画について「業界にないフレッシュな発想が、最大のメリット」という。スケッチツアー以外の企画もユニークで、例えばタヒチの黒真珠養殖と日本の養殖技術の高さに着目し、タヒチで就労を希望する中国人労働者を日本で技術を身につけてもらい、タヒチに送るという真珠養殖プランや、日本でのタヒチアン・ダンスの流行とスポーツクラブに目を付け、他社との差別化をはかるためのインストラクター養成ツアーの案もあった。「業界にいるとマーケットとして取り上げないことかもしれないが、それを研究してくれたとことで複眼的な考察が得られた」と中村さんは評価する。
インターンシップで学生の実務を担当し、今回の実地調査にも同行したTN旅客営業部の中村真樹さんは今回の協同同企画について「業界にないフレッシュな発想が、最大のメリット」という。スケッチツアー以外の企画もユニークで、例えばタヒチの黒真珠養殖と日本の養殖技術の高さに着目し、タヒチで就労を希望する中国人労働者を日本で技術を身につけてもらい、タヒチに送るという真珠養殖プランや、日本でのタヒチアン・ダンスの流行とスポーツクラブに目を付け、他社との差別化をはかるためのインストラクター養成ツアーの案もあった。「業界にいるとマーケットとして取り上げないことかもしれないが、それを研究してくれたとことで複眼的な考察が得られた」と中村さんは評価する。
庄司准教授も「学生は業界が思いもよらないアイディアを出すこともできるし、若さを生かした機動力もある。ただ、仮に企画を具体化するとしても、その方法や判断が難しい」という。一方、業界では仮にアイディアがあるとしても試作品にするまでの手間を考え、コストを量りにかけて、実現しない例もある。企画に関してはこの部分を補完しあうことが、産学連携でできるメリットのひとつだという。
双方の意義を理解せずにメリットなし−人材確保は業界の課題
 庄司准教授はTNとのインターンシップに対し「しっかり見てくれて、鍛えてもらった。企業が責任を持ってやってくれること大切で、安い労働力という感覚では無意味」と大学にとっての意義を語る。一方、実務を担当したTN中村さんも「学生の個性や能力を見て仕事を決め、徐々に仕事の範囲を広げていった」と、工夫を伝えるとともに、「アルバイト感覚でなく、社会のプレイニシエーションの心構えで来てほしい。あらかじめ業界の情報を理解していれば、もっと有意義な経験ができると思う」とアドバイスする。
庄司准教授はTNとのインターンシップに対し「しっかり見てくれて、鍛えてもらった。企業が責任を持ってやってくれること大切で、安い労働力という感覚では無意味」と大学にとっての意義を語る。一方、実務を担当したTN中村さんも「学生の個性や能力を見て仕事を決め、徐々に仕事の範囲を広げていった」と、工夫を伝えるとともに、「アルバイト感覚でなく、社会のプレイニシエーションの心構えで来てほしい。あらかじめ業界の情報を理解していれば、もっと有意義な経験ができると思う」とアドバイスする。
 今、観光関連の学部を卒業した学生が旅行業界に入社するのは約3割と言われている。「身近な先輩が旅行会社で苦労している姿を見て」「労働条件が悪い」といった理由が多いようだ。今回の3名も残念ながら、業界外の企業への道を選んだ。せっかく、産学協同で業界の内部を知り、即戦力に近い人材になっても、他業界に進んでしまっては大きな損失。学生にとって魅力的な業界であることは、業界の課題であるといえる。
今、観光関連の学部を卒業した学生が旅行業界に入社するのは約3割と言われている。「身近な先輩が旅行会社で苦労している姿を見て」「労働条件が悪い」といった理由が多いようだ。今回の3名も残念ながら、業界外の企業への道を選んだ。せっかく、産学協同で業界の内部を知り、即戦力に近い人材になっても、他業界に進んでしまっては大きな損失。学生にとって魅力的な業界であることは、業界の課題であるといえる。
一方、立教大学では07年、「ツーリズム・イノベーターの戦略的育成」プログラムを掲げ、大学から今後のツーリズムの新機軸を提示できる人材を育てる取り組みに着手。文部科学省の「大学院教育改革支援プログラム」にも採択されている。大学から業界に働きかけようという取り組みで、今後の動きに注目したい。
▽立教大学 ツーリズム・イノベーターの戦略的育成
http://www.tr.rikkyo.ac.jp/graduate/ria.php
〜新鮮な視点と機動力で生まれた、タヒチ・スケッチ・ツアー〜
 エア・タヒチ・ヌイ(TN)と立教大学の庄司准教授ゼミナールでは、2006年からインターンシップを開始。この作業中の会話から企画の提案が持ち上がり、正式に庄司ゼミでの研究テーマに「新しいセグメント(顧客層)へのタヒチ旅行」が取り上げられた。課題は(1)TNの搭乗客を増やすこと、(2)パペーテを売ること、の2つ。これにより生まれた今回の企画「スケッチ・ツアー」は、学生の発想と機動力に業界の経験が合致した成功例といえる。企画内容に対する実地調査に同行し、そこで垣間見た産学連携の効果と今後の課題をレポートする。
エア・タヒチ・ヌイ(TN)と立教大学の庄司准教授ゼミナールでは、2006年からインターンシップを開始。この作業中の会話から企画の提案が持ち上がり、正式に庄司ゼミでの研究テーマに「新しいセグメント(顧客層)へのタヒチ旅行」が取り上げられた。課題は(1)TNの搭乗客を増やすこと、(2)パペーテを売ること、の2つ。これにより生まれた今回の企画「スケッチ・ツアー」は、学生の発想と機動力に業界の経験が合致した成功例といえる。企画内容に対する実地調査に同行し、そこで垣間見た産学連携の効果と今後の課題をレポートする。(取材協力:・エア・タヒチ・ヌイ、タヒチ観光局、メリディアン・タヒチ、シェラトン・モーレア・ラグーン・リゾート&スパ)
▽関連記事
◆現地レポート−タヒチ スケッチ・ツアーを皮切りに、シニア向け素材に注目(2008/03/27)
◆フォトニュース−タヒチ、シニアの絵心を刺激する景色と雰囲気にあふれた島々(2008/03/28)
身近な話題から課題を提供、モチベーション向上
 きっかけは、ゼミ生の渡辺菜穂さんがインターンシップをしていた当時、話題のテレビドラマ「電車男」の特別編がタヒチで撮影されることから、TNマーケティング本部長の柳川悦子氏に「このドラマがタヒチのプロモーションになると思うか」と聞かれたこと。渡辺さんは「テレビに露出することで何かしら効果になると思う。ただ、時間とお金がないと難しいし、もう一つ何かがないとタヒチにまで行こうと思わないのでは」と意見を述べたところ、「それが何か、考えて欲しい」と課題が与えられた。そこで06年度の終わりごろ、ゼミの研究課題に設定。渡辺さんとゼミ生の正木賢輔さん、直井廉東さんは企画に乗り出した。「まさか学生に企画を任せくれるなんて」と、モチベーションが高まったという。
きっかけは、ゼミ生の渡辺菜穂さんがインターンシップをしていた当時、話題のテレビドラマ「電車男」の特別編がタヒチで撮影されることから、TNマーケティング本部長の柳川悦子氏に「このドラマがタヒチのプロモーションになると思うか」と聞かれたこと。渡辺さんは「テレビに露出することで何かしら効果になると思う。ただ、時間とお金がないと難しいし、もう一つ何かがないとタヒチにまで行こうと思わないのでは」と意見を述べたところ、「それが何か、考えて欲しい」と課題が与えられた。そこで06年度の終わりごろ、ゼミの研究課題に設定。渡辺さんとゼミ生の正木賢輔さん、直井廉東さんは企画に乗り出した。「まさか学生に企画を任せくれるなんて」と、モチベーションが高まったという。単価30万円から40万円の60万人市場、データで有用性を証明
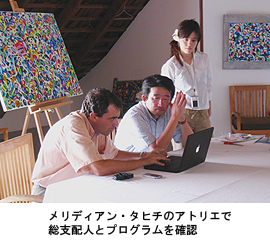 消費者調査では「高額で行けないけど、いつか行きたい」との声が多い一方で、タヒチで何ができるか、どこにあるのかさえ知られていないことが判明。ターゲットをリタイアしたシニアとし、具体的なタヒチ旅行の切り口を探しはじめた。また、シニアから「仕事や子育てを終えて生きがいになることをしたいけれど、自分が今、何をしたいのか分からず、淋しくなるときがある」という答えが多いことも印象的だった。そこで注目したのが、画家・ポール・ゴーギャン。「ゴーギャンが第2の人生を始めたこの地でのんびり考えれば、生活に追われて忘れていた自分を取り戻すきっかけになるのでは」と思いついた。
消費者調査では「高額で行けないけど、いつか行きたい」との声が多い一方で、タヒチで何ができるか、どこにあるのかさえ知られていないことが判明。ターゲットをリタイアしたシニアとし、具体的なタヒチ旅行の切り口を探しはじめた。また、シニアから「仕事や子育てを終えて生きがいになることをしたいけれど、自分が今、何をしたいのか分からず、淋しくなるときがある」という答えが多いことも印象的だった。そこで注目したのが、画家・ポール・ゴーギャン。「ゴーギャンが第2の人生を始めたこの地でのんびり考えれば、生活に追われて忘れていた自分を取り戻すきっかけになるのでは」と思いついた。その時、庄司准教授に「日本人には何もしない旅行は難しい」という話を聞き、ゴーギャンの「絵」に目を向けた。自分で描く喜びだけでなく、制作に時間を使うこともポイントだ。調べてみるとシニアの絵画愛好家が約60万人の市場であることが推察できた。そこで、07年7月のプレゼンでは「その1%でも6000人。30万円から40万円の単価ならインパクトある」と強調。切り口とデータ証明がTNの目に留まり、本格的に企画化に向けて動くことになった。渡辺さんはプレゼンについて「(TNの)日本支社長まで同席してくれたことに感激した」と言う。企業側の真摯な態度が、学生の本気度をさらに動かすといえるだろう。
現場の大切さ学ぶ場に
 正木さんは「企画段階では、エア・タヒチ・ヌイさんは突拍子もない発想を期待していると思い、気が楽だった。でも、具体化に向けて走り出すと、航空会社ホテルなど、1つの商品を作るのに、いろいろな人が関わって、調整しながら動いていることを知った。これはゼミの研究だけでは分からなかったこと」と実感を語る。
正木さんは「企画段階では、エア・タヒチ・ヌイさんは突拍子もない発想を期待していると思い、気が楽だった。でも、具体化に向けて走り出すと、航空会社ホテルなど、1つの商品を作るのに、いろいろな人が関わって、調整しながら動いていることを知った。これはゼミの研究だけでは分からなかったこと」と実感を語る。実地調査でも学んだ点が多かった。同行したプレスツアーの参加者に企画のターゲットと同年代の参加者がいたが、視察であちこち巡るうち、かなり疲労していた。それを見た直井さんは「この日程のままではお客様は満足しない。現場を自分の足で回ることは大切」と感じたという。渡辺さんは「滞在先からスケッチポイントまでは思った以上に距離があり、個人旅行者が自分で行くのは難しい。手配が課題になると思う」としながらも、「タヒチの生活を見て日本人と価値観が違うことを感じ、いろんな生き方があることに気付いた。ツアーを通してそんな面も感じてもらえれば、大きな財産を提供できるのでは」と、課題とともに企画のもつ新たな魅力に気付いたようだ。
互いの強みと得意分野で弱点を補完し、業務の幅を拡充
 インターンシップで学生の実務を担当し、今回の実地調査にも同行したTN旅客営業部の中村真樹さんは今回の協同同企画について「業界にないフレッシュな発想が、最大のメリット」という。スケッチツアー以外の企画もユニークで、例えばタヒチの黒真珠養殖と日本の養殖技術の高さに着目し、タヒチで就労を希望する中国人労働者を日本で技術を身につけてもらい、タヒチに送るという真珠養殖プランや、日本でのタヒチアン・ダンスの流行とスポーツクラブに目を付け、他社との差別化をはかるためのインストラクター養成ツアーの案もあった。「業界にいるとマーケットとして取り上げないことかもしれないが、それを研究してくれたとことで複眼的な考察が得られた」と中村さんは評価する。
インターンシップで学生の実務を担当し、今回の実地調査にも同行したTN旅客営業部の中村真樹さんは今回の協同同企画について「業界にないフレッシュな発想が、最大のメリット」という。スケッチツアー以外の企画もユニークで、例えばタヒチの黒真珠養殖と日本の養殖技術の高さに着目し、タヒチで就労を希望する中国人労働者を日本で技術を身につけてもらい、タヒチに送るという真珠養殖プランや、日本でのタヒチアン・ダンスの流行とスポーツクラブに目を付け、他社との差別化をはかるためのインストラクター養成ツアーの案もあった。「業界にいるとマーケットとして取り上げないことかもしれないが、それを研究してくれたとことで複眼的な考察が得られた」と中村さんは評価する。庄司准教授も「学生は業界が思いもよらないアイディアを出すこともできるし、若さを生かした機動力もある。ただ、仮に企画を具体化するとしても、その方法や判断が難しい」という。一方、業界では仮にアイディアがあるとしても試作品にするまでの手間を考え、コストを量りにかけて、実現しない例もある。企画に関してはこの部分を補完しあうことが、産学連携でできるメリットのひとつだという。
双方の意義を理解せずにメリットなし−人材確保は業界の課題
 庄司准教授はTNとのインターンシップに対し「しっかり見てくれて、鍛えてもらった。企業が責任を持ってやってくれること大切で、安い労働力という感覚では無意味」と大学にとっての意義を語る。一方、実務を担当したTN中村さんも「学生の個性や能力を見て仕事を決め、徐々に仕事の範囲を広げていった」と、工夫を伝えるとともに、「アルバイト感覚でなく、社会のプレイニシエーションの心構えで来てほしい。あらかじめ業界の情報を理解していれば、もっと有意義な経験ができると思う」とアドバイスする。
庄司准教授はTNとのインターンシップに対し「しっかり見てくれて、鍛えてもらった。企業が責任を持ってやってくれること大切で、安い労働力という感覚では無意味」と大学にとっての意義を語る。一方、実務を担当したTN中村さんも「学生の個性や能力を見て仕事を決め、徐々に仕事の範囲を広げていった」と、工夫を伝えるとともに、「アルバイト感覚でなく、社会のプレイニシエーションの心構えで来てほしい。あらかじめ業界の情報を理解していれば、もっと有意義な経験ができると思う」とアドバイスする。 今、観光関連の学部を卒業した学生が旅行業界に入社するのは約3割と言われている。「身近な先輩が旅行会社で苦労している姿を見て」「労働条件が悪い」といった理由が多いようだ。今回の3名も残念ながら、業界外の企業への道を選んだ。せっかく、産学協同で業界の内部を知り、即戦力に近い人材になっても、他業界に進んでしまっては大きな損失。学生にとって魅力的な業界であることは、業界の課題であるといえる。
今、観光関連の学部を卒業した学生が旅行業界に入社するのは約3割と言われている。「身近な先輩が旅行会社で苦労している姿を見て」「労働条件が悪い」といった理由が多いようだ。今回の3名も残念ながら、業界外の企業への道を選んだ。せっかく、産学協同で業界の内部を知り、即戦力に近い人材になっても、他業界に進んでしまっては大きな損失。学生にとって魅力的な業界であることは、業界の課題であるといえる。一方、立教大学では07年、「ツーリズム・イノベーターの戦略的育成」プログラムを掲げ、大学から今後のツーリズムの新機軸を提示できる人材を育てる取り組みに着手。文部科学省の「大学院教育改革支援プログラム」にも採択されている。大学から業界に働きかけようという取り組みで、今後の動きに注目したい。
▽立教大学 ツーリズム・イノベーターの戦略的育成
http://www.tr.rikkyo.ac.jp/graduate/ria.php