「北海道に根を張り、外貨を稼ぐ」地域とともに歩む観光業のかたち-北海道宝島旅行社代表取締役社長 鈴木宏一郎氏
鈴木 2025年1月、英語版の体験予約サイト「All Hokkaido」を再始動しました。日本語での予約が難しい海外顧客にも地域の体験を届けたいという思いからです。背景には、日本人旅行客が減少し、またホテル代の高騰によって体験にかけられる予算が減っている現状があります。そうしたなかで、地元のガイドさんや体験事業者さんたちが持続可能に活動を続けていくためには、インバウンド需要の獲得が必要です。ただし、すべての事業者が英語対応できるわけではないので、その部分は私たちが部分的にサポートしていきます。
一般的なOTAよりも安めに手数料を設定しています。経費を差し引けば利益は出ないのですが、これは根幹事業ですし、地元の体験事業者やガイドさんたちのために必要だから続けようと決意しました。
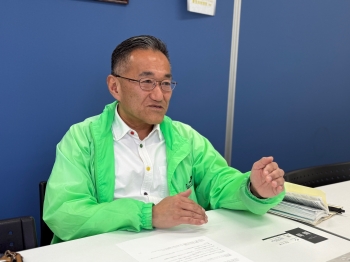
鈴木 現在、取り扱っているお客様の国籍比率としては、シンガポールが全体の約半分弱を占めており、東南アジア諸国を合わせて7割程度になります。残りの3割が欧米やオーストラリアからのお客様です。英語が通じるお客様に限定して、オーダーメイドの旅行サービスを提供しています。
実際に来られたお客様の例としては、ハワイからの大人数のリピーターさんや、シンガポールから訪れたすごい富裕層のお客様などが印象に残っています。今年の年明けに来道されたフィリピンのお客様は10数名で一週間、道内各地を周遊して、飛行機代を除いて1000万円の旅行になりました。
オーダーメイドの旅行サービスではヒアリングを徹底していて、お客様とのメールでのやりとりは50〜100回に及ぶこともあります。ビーガンやLGBTQ、医療的ケアが必要な方など、多様なニーズに応じて旅を設計しています。ビーガンのお客様で旅行中に誕生日を迎える方がいるときは、お寿司屋さんに野菜を使ったバースデーケーキ風寿司を作ってもらったりもしています。
基本的には北海道専門で、他地域への対応はしていません。東京や京都に行きたいというご要望には、信頼できる仲間をご紹介する程度です。土着している北海道でしか提供できないクオリティにこだわっています。
鈴木 はい。「モニターツアーを作って終わり」の成果物型観光資源ではなく、「実際に継続的にお客様を送り込む」ことまでを重視しています。北海道運輸局や北海道観光機構、市町村等と連携して、実働型の観光コンサルティングを行っています。
また、JARTA(日本の責任ある旅行会社の協議会)の立ち上げメンバーとして、旅行会社の認証制度「トラベルライフ」などの普及にも関わっています。「100点を目指さなくていい。まずは30点からでも少しずつ」という考え方に共鳴して、現場が取り組みやすい環境をつくることを心がけています。
鈴木 やはり旅というものは、誰が言う必要もなく素晴らしいものですよね。地域に外貨をもたらし、地元の人の誇りも育てられる。だけど、今は、それを支える観光業の人たちの給料が安すぎる。優秀な人材が集まらないのも当然です。私たちも給与や休日日数を見直していますがまだまだ。業界全体が「もっと稼げる」仕組みに変わらなければいけないと思います。また、募集型旅行で、お客さんと約束した予定が少しでも変更されたら補償の対象となるリスクがある現在の旅行業法も変えなきゃいけない。安さを追求する募集型企画旅行から、高い付加価値を提供する受注型企画旅行へ。もっと付加価値をあげていきましょう。それが地域のためにも、自分たちの未来のためにもなるはずです。
お薦めの飲食店については、大切な知り合いが札幌に来たら連れて行く、何を食べても美味しい「魚と肴おうぎや」と、「紫雲亭」というラーメン屋さんです。わたしはもっぱら塩ラーメンを頼みます。