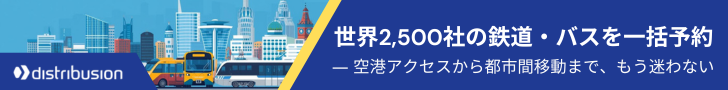取材ノート:地域活性化と旅行業の役割−着地型観光と新ビジネスモデル
 旅行業と地域活性化の結びつきに対する関心が高まっている。これまでの旅行業は、各店舗から消費者を旅行に送り出す発地型を主としていた。しかし今、旅行者を地域に呼び込む着地型観光を含めたビジネスモデルが、可能性を探られている。元気のいい地域は観光資源そのもの。旅行業は地域の魅力磨きにどのような貢献ができるだろうか。JATA経営フォーラム2011の分科会では、「地域活性化で旅行業もいきいき!〜地域活性化事業の現状と今後のビジネスモデル」と題するパネルディスカッションで、旅行業と地域づくりの相乗効果について考察された。
旅行業と地域活性化の結びつきに対する関心が高まっている。これまでの旅行業は、各店舗から消費者を旅行に送り出す発地型を主としていた。しかし今、旅行者を地域に呼び込む着地型観光を含めたビジネスモデルが、可能性を探られている。元気のいい地域は観光資源そのもの。旅行業は地域の魅力磨きにどのような貢献ができるだろうか。JATA経営フォーラム2011の分科会では、「地域活性化で旅行業もいきいき!〜地域活性化事業の現状と今後のビジネスモデル」と題するパネルディスカッションで、旅行業と地域づくりの相乗効果について考察された。●モデレーター
日本観光協会常務理事・総合研究所長 丁野朗氏
●パネリスト
ジェイティービー法人営業部長・地域交流ビジネス推進室長 加藤誠氏
リクルート旅行カンパニーじゃらんリサーチセンター長 沢登次彦氏
京都嵯峨芸術大学芸術学部観光デザイン学科教授 真板昭夫氏▽関連記事
◆旅行会社は地域と旅行者のギャップマネージメントを−JATA経営フォーラム(2011/02/18)
ニーズの変化で「街歩き」人気
マスツーリズムからの脱却を
 「現在の消費者はどのような旅行を求めているだろうか」。冒頭で丁野氏が問いかけると、沢登氏は宿泊旅行の目的として「街歩き」「名所・旧跡」「地元の食」といったキーワードが上昇しているとの調査結果を報告した。一方、「温泉」は年々微減傾向にある。沢登氏は「温泉や宿といったハードの観光資源からソフト面へと興味が移っており、アクティブで目的型の旅行が増えている」と現状を分析する。
「現在の消費者はどのような旅行を求めているだろうか」。冒頭で丁野氏が問いかけると、沢登氏は宿泊旅行の目的として「街歩き」「名所・旧跡」「地元の食」といったキーワードが上昇しているとの調査結果を報告した。一方、「温泉」は年々微減傾向にある。沢登氏は「温泉や宿といったハードの観光資源からソフト面へと興味が移っており、アクティブで目的型の旅行が増えている」と現状を分析する。加藤氏は、「1990年代までのマス・プロダクト型では、もはや消費者の関心を得られない」とニーズの多様化を指摘。同時に、あらゆる業界で全体的に品質が向上し、性能や価格での差別化が難しくなったともいう。現代では「作り手が発信するデザインの役割がことさら大きい」と加藤氏は強調し、「ホテルや航空券の組み合わせだけで売れた時代」から、「五感に訴えるシナリオづくり」を担う「旅をデザインする時代」に入ったと告げる。
感動を創る旅のポイントとして、パネリスト全員が一致して最初に掲げたのは、地元の人自身の「ご当地愛」の形成だ。沢登氏は、まず地域内をよく知るための「インターナルマーケティング」をしっかり実施する必要があると述べる。第2のポイントは、対象となる消費者を絞り込む「マイクロターゲット」。マスよりもニッチな市場を極めることだという。第3は、期待値とそれを超える満足度との「ギャップ」。今まであまり知られていなかったところほど思いがけない満足につながり、リピーターが生まれやすいと沢登氏は語る。
磨いて誇る地域の「宝」
旅行会社は価値を伝えるパートナー
 真板氏は、「地域の魅力や自慢を伝える手段を持たない地元の人に代わって、旅行業者がその価値を伝える」という「観光デザイン」の概念を提示する。目標は、「地域の価値(誇りや自慢)の共有化と郷土意識の育成」だ。真板氏によると、地域には「自然」、「生活環境(生きるための知恵の体系)」、「歴史・文化」、「産業」、「名人(地域の知恵袋)」という5つの宝がある。地域の人からは、「その宝が外部の人にも喜ばれるものかどうか教えてほしい」と旅行業者に対して切に望む声が聞かれるという。
真板氏は、「地域の魅力や自慢を伝える手段を持たない地元の人に代わって、旅行業者がその価値を伝える」という「観光デザイン」の概念を提示する。目標は、「地域の価値(誇りや自慢)の共有化と郷土意識の育成」だ。真板氏によると、地域には「自然」、「生活環境(生きるための知恵の体系)」、「歴史・文化」、「産業」、「名人(地域の知恵袋)」という5つの宝がある。地域の人からは、「その宝が外部の人にも喜ばれるものかどうか教えてほしい」と旅行業者に対して切に望む声が聞かれるという。「宝探し」は、宝を探し、磨き、誇り、伝え、さらに活かして新たなブランドを生み出すという流れによって、「地域づくり」へと展開する。ブランドづくりの際は、「なぜこの地域なのか」「なぜこのデザインなのか」に答える「理念の確立」が必須だと真板氏は述べる。地域独特の商品であることを主張する「正当性」も重要だ。これに対して会場からは、「たとえば海がない土地でフグを売りにするなど、資源がない土地でよそから観光素材を持ってくるのはどうか」との質問が出た。真板氏は、「その方法も可能だが、『ご当地愛』をベースとし、地元とのつながり、由緒を明らかにすることが重要。単なるよそのマネでは、ブランドとして持続性がない」と解説する。
さらに真板氏は、「肝心なのは地元の人が本当に楽しめるかどうか。観光客に媚びへつらわない態度が大切」と続ける。沢登氏と同様、「地元の人がすばらしさを認め、誇りを高めることが先で、観光客を呼ぶのはその後」と述べ、あくまでも地元中心・先導主義を重視。旅行会社は、地域のパートナーという位置付けだ。
地域と消費者のギャップマネージメント
コーディネーターとしての役割
 会場からはまた、「たとえば九州では味噌も醤油も甘いが、東京の人はそれに拒否反応を示すことがある。地元の価値と消費者のニーズ、どちらを優先させるか」との質問も挙がった。沢登氏はこれに答え、「まずは地域の価値を大事にすべき。土地の文化を経験することが旅。ただ、『九州の味噌は甘いですよ』と伝えておくことが大切」と述べる。加藤氏も、「観光業が売るのは味噌ではなく経験」と応じた。時には、観光客に良いと思って提供するものが見当違いだったり、求められるレベルに至らない場合もある。旅行業が地域に果たす役割は、旅行者ニーズと地域とのギャップマネージメントだ。真板氏は、「各地域から商品を持ち寄り、旅行業者や地域コーディネーターとともに評価、批判し合う『楽市楽座』を設けては」と、BtoBのマーケットづくりを提唱。期待を上回るような「ギャップ」を磨く場とする考えだ。
会場からはまた、「たとえば九州では味噌も醤油も甘いが、東京の人はそれに拒否反応を示すことがある。地元の価値と消費者のニーズ、どちらを優先させるか」との質問も挙がった。沢登氏はこれに答え、「まずは地域の価値を大事にすべき。土地の文化を経験することが旅。ただ、『九州の味噌は甘いですよ』と伝えておくことが大切」と述べる。加藤氏も、「観光業が売るのは味噌ではなく経験」と応じた。時には、観光客に良いと思って提供するものが見当違いだったり、求められるレベルに至らない場合もある。旅行業が地域に果たす役割は、旅行者ニーズと地域とのギャップマネージメントだ。真板氏は、「各地域から商品を持ち寄り、旅行業者や地域コーディネーターとともに評価、批判し合う『楽市楽座』を設けては」と、BtoBのマーケットづくりを提唱。期待を上回るような「ギャップ」を磨く場とする考えだ。また、加藤氏は、地域と旅行会社間にあるギャップにも言及。「地域の人は、宝を探したら旅行会社が必ず売ってくれると信じている」と語る。旅行会社はニーズや旅行業の現状を地域の人に伝え、相互理解を深めていく必要がある。旅行業は「地域のコンサルタンティング事業」(加藤氏)であり、旅行会社には「地域ブランドづくりのトータルコーディネーター」(真板氏)の姿が求められている。今後は、そのための人材育成が課題だという。
加藤氏によると、JTBでは2011年度からの事業ドメインに「地域交流事業」を掲げているほか、ホスピタリティ教育も含めてデスティネーションをプロデュースする人材育成講座を設置しているという。「我々も多くの経験をしないと、魅力を判断することができない。もっと自ら地域に深く入るべき」と加藤氏は指摘した。
周辺ビジネスに裾野拡大
業種、会社の枠を超えた改革を
 丁野氏は、「地域発の新ビジネスと旅行業の関わり」との視点も提起する。真板氏は、南大東島で特産のサトウキビを活用し、ラム酒を開発した事例を紹介した。島の食文化とともにラム酒を楽しんでもらうよう、東京のバーテンダーも協力して取り組んだという。沢登氏は、「地域の魅力を最もよく知る人になれば、消費者と地域を結ぶさまざまなビジネスが生まれてくる」と展望する。
丁野氏は、「地域発の新ビジネスと旅行業の関わり」との視点も提起する。真板氏は、南大東島で特産のサトウキビを活用し、ラム酒を開発した事例を紹介した。島の食文化とともにラム酒を楽しんでもらうよう、東京のバーテンダーも協力して取り組んだという。沢登氏は、「地域の魅力を最もよく知る人になれば、消費者と地域を結ぶさまざまなビジネスが生まれてくる」と展望する。さらに、旅行中のペットや植木の世話、託児所、介護サービスなど、旅行業の裾野を広げる周辺ビジネスについても意見が求められた。加藤氏は、「出発から帰着までの新しいバリューチェーンを旅行業界内の数社協働でつくる」という構想を提案。「競争だけでなく、旅行会社同士で『共争』して共につくる価値もある。オープンイノベーションを起こすべきでは」と語る。丁野氏は、「地域内にも業界内にも、オープンイノベーションができる風土づくりを仕掛けていきたい」と、期待を示した。
取材:福田晴子