取材ノート:海外旅行需要の低迷をチャンスへ、在日観光局からの提言
 日本人の海外旅行者増加に向けて、今やるべきこととは何か。在日外国観光局協議会(ANTOR−JAPAN)は今年のJATA世界旅行博で、「海外旅行需要の低迷をいかにチャンスに変えるか」と題するシンポジウムを開催。日本市場を包括的に分析したパネリストとして登壇したのは、ANTOR−JAPAN会長(香港政府観光局日本・韓国地区局長)の加納國雄氏、ハンガリー政府観光局局長のコーシャ・バーリン・レイ氏、ドイツ観光局アジア・オーストラリア地区統括局長のペーター・ブルーメンシュテンゲル氏、グアム政府観光局日本代表の光森裕二氏。モデレーターは、ANTOR−JAPAN副会長でUSトラベル・アソシエーション日本代表の井上嘉世子氏が務めた。熱く論じられた数々の提言を紹介する。
日本人の海外旅行者増加に向けて、今やるべきこととは何か。在日外国観光局協議会(ANTOR−JAPAN)は今年のJATA世界旅行博で、「海外旅行需要の低迷をいかにチャンスに変えるか」と題するシンポジウムを開催。日本市場を包括的に分析したパネリストとして登壇したのは、ANTOR−JAPAN会長(香港政府観光局日本・韓国地区局長)の加納國雄氏、ハンガリー政府観光局局長のコーシャ・バーリン・レイ氏、ドイツ観光局アジア・オーストラリア地区統括局長のペーター・ブルーメンシュテンゲル氏、グアム政府観光局日本代表の光森裕二氏。モデレーターは、ANTOR−JAPAN副会長でUSトラベル・アソシエーション日本代表の井上嘉世子氏が務めた。熱く論じられた数々の提言を紹介する。日本の課題は慢性的、社会全体に風穴を
 日本人の出国率低迷の理由としては一般に、金融危機や燃油価格の高騰などがあげられている。しかしこれらは世界各国でも共通する要因だ。その中でも台湾の出国率は上昇傾向にあり、韓国も日本より高いという。ドイツ観光局のブルーメンシュテンゲル氏は、「日本市場に特化した原因を探らなければならない」と述べる。
日本人の出国率低迷の理由としては一般に、金融危機や燃油価格の高騰などがあげられている。しかしこれらは世界各国でも共通する要因だ。その中でも台湾の出国率は上昇傾向にあり、韓国も日本より高いという。ドイツ観光局のブルーメンシュテンゲル氏は、「日本市場に特化した原因を探らなければならない」と述べる。日本の特徴としてブルーメンシュテンゲル氏が最初に指摘するのは、「休みがないこと」だ。「人々が旅をしない本当の理由は、長期休暇を認められない雇用者の労働環境にある。これは非常に重要な問題」と強調。「もし20日間の休みがあれば、誰もが旅行に行くだろう」と語る。2007年のJNTO(日本政府観光局)の資料によると、休暇を確保できるドイツの出国者数は、国際ランキングで世界1位だ。
ハンガリー政観のレイ氏は、「日本の出国率低迷は慢性的な課題。経済より社会的要因が大きいのでは」と問う。休暇はないというより「あっても取れない雰囲気」だと言及。不況や新型インフルエンザの流行でも、実態以上に「今は海外旅行どころではないとの風潮」にとらわれていると見る。例えばハンガリーでは新型インフルエンザの発症がゼロだったが、日本からの渡航者は減少した。グアム政観の光森氏によるとグアムでも、SARSの際は被害がなかったにもかかわらず日本人が減っている。「背景には海外の安全情報の欠如による判断ミスも含まれる」と、レイ氏は考察する。
商品力強化の鍵は、積極的な現地視察
 シンポジウムでは、視察の重要性も繰り返された。ブルーメンシュテンゲル氏は、現地を訪れないまま業務に携わっている旅行会社スタッフが多い状況に疑問を提示。「現地事情は行って見なければ分からない。担当者を積極的に海外に送ることが必要」と語る。
シンポジウムでは、視察の重要性も繰り返された。ブルーメンシュテンゲル氏は、現地を訪れないまま業務に携わっている旅行会社スタッフが多い状況に疑問を提示。「現地事情は行って見なければ分からない。担当者を積極的に海外に送ることが必要」と語る。レイ氏も、「旅行会社にもハンガリーの隣にクロアチアがあると知らない人は多い。認識があれば、2ヶ国周遊など新しい商品造成につながるはず」と述べている。「現在のパッケージは画一化し、多様な層に向けた多様なツアーに欠ける」との見解だ。ターゲットの細分化、リピーターに向けたユニークな企画やFIT商品、セミFIT商品の充実が求められるという。
香港政観の加納氏も「商品力の強化」を重点課題にあげる。「素材は我々が用意する」との姿勢で、「旅行会社にとってどのようなFAMツアーが良いか、意見がほしい」と呼びかける。FAMツアーは「貴重なビジネスマッチングの場」であり、参加者が少ない現状を打開したい考えだ。
長期の取り組みでイメージアップ
 日本の慢性的な社会要因としてレイ氏は、「海外旅行がかっこいいと思われなくなったようだ」と、イメージの変化にも言及。統計では特に若年層の旅行者数減少が著しい上、周囲の反応を見ても海外に対する憧れが薄れたようで、流行の移り変わりを実感するという。イメージアップには長期的な視野が欠かせないとの意見だ。
日本の慢性的な社会要因としてレイ氏は、「海外旅行がかっこいいと思われなくなったようだ」と、イメージの変化にも言及。統計では特に若年層の旅行者数減少が著しい上、周囲の反応を見ても海外に対する憧れが薄れたようで、流行の移り変わりを実感するという。イメージアップには長期的な視野が欠かせないとの意見だ。そのようななか、この10年間の「イメージ変革によるリブランディング」で成果を示すのが、グアムだ。「グアムの海はナマコが多い」といったイメージを改善するため、プロモーションやセミナーで精力的な努力を続けた結果、これまでと一転して、今年はリピーターや高所得階級の渡航者が増えたという。
成功した施策のひとつは、旅行会社の店舗を訪れてサポートを依頼する、GALC(グアムアンバサダー・アット・ラージ・キャラバン)。大手旅行会社の部長自身がピーアールシャツを着て参加し、社員のモチベーションをあげてくれたという。また、航空会社や旅行会社との話しあいの場として、JGTC(ジャパン・グアム・ツーリズム・コミッティ)を構成。各社で課題を共有し、グアムに就航している地方自治体との連携も強めた。「観光局だけでは進まない。官民一体で仕事をする、『ワーク・トゥギャザー』が成功の秘訣」と光森氏は語る。
渡航者数より「旅の価値」に指標をシフト
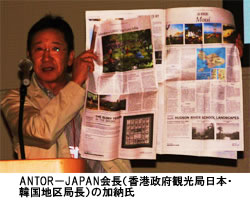 金融危機や感染症による突発的な落ち込みは、一時が過ぎれば回復する。日本市場で気になるのはむしろ、ゆるやかな減少傾向だ。根本的な対策は、次世代を見据えた「旅の価値の見直し」ではないだろうか。レイ氏は、「若年層では就職に有利なインターンシップに参加する人が増えており、自分の将来にプラスになることをしたいという要望はある。海外旅行にその価値があれば行くようになるのでは」と進言。「渡航者数を増やすことばかりに気をとられがちだが、それは必須ではない。内容の充実や宿泊数の増加によるビジネスモデルが可能」と見ており、「付加価値を高め、もっと違う経験を提供することが現在できる近道」と語る。
金融危機や感染症による突発的な落ち込みは、一時が過ぎれば回復する。日本市場で気になるのはむしろ、ゆるやかな減少傾向だ。根本的な対策は、次世代を見据えた「旅の価値の見直し」ではないだろうか。レイ氏は、「若年層では就職に有利なインターンシップに参加する人が増えており、自分の将来にプラスになることをしたいという要望はある。海外旅行にその価値があれば行くようになるのでは」と進言。「渡航者数を増やすことばかりに気をとられがちだが、それは必須ではない。内容の充実や宿泊数の増加によるビジネスモデルが可能」と見ており、「付加価値を高め、もっと違う経験を提供することが現在できる近道」と語る。加納氏が注目するのは、「旅の価値を伝える『コミュニケーション力』」だ。「ニューヨークタイムズの旅行欄には、行きたいという夢を見させるような、すばらしい記事がある。日本の新聞の旅行広告は、ただ値段と行き先が載っているだけ。これでは旅行の楽しさが伝わらない」と述べ、ウェブ、パンフレット、フリーペーパーといったメディアの活用を訴える。目的は、旅行検討段階にある消費者への動機付け。値段と行程を詰め込んだ従来の旅行パンフレットから、旅行に興味のない層にも手を取らせて心を揺さぶるような媒体へと、脱却をめざす提案だ。ここでも「観光局と旅行会社の連携が肝要」と加納氏は述べる。
「休暇の確保」、「イメージの改善」、「付加価値の高い、多様な商品造成」や、「新しいメディア・プロモーション」。海外旅行需要増大のためにあがったさまざまなポイントに共通するキーワードは、旅行会社や観光局、各国政府、自治体などとの官民を超えた「幅広い連携」といえそうだ。既存の慣習にとらわれず、日本市場の体質改善が求められる。ブルーメンシュテンゲル氏は、「悲観視せず、旅行業界からポジティブな情報発信を」と意欲付けた。
取材:福田晴子