旅行業の生き残り戦略とは、異業種の事例に学ぶ−JATA経営フォーラム
 2月24日に開催されたJATA経営フォーラム2009のパネルディスカッションは、「旅行業、生き残り戦略とは!−他業種からヒントを掴め−」がテーマ。コメンテーターにはとバス代表取締役社長の松尾均氏、富士フィルムのヘルスケア事業統括本部ライフサイエンス事業部営業部長の杉本和繁氏、香港のEGL tours董事総経理の袁文英氏が出席し、各社が直面した経営危機と生き残り戦略について、興味深い経験を語った。異業種とはいえ、各社が経験した危機は旅行業界にとって人ごとではなく、各社のユニークな取り組みは今後の経営のヒントになり得るものが多かった。モデレーターを務めたのは、ツーリズム・マーケティング研究所の取締役マーケティング部長の高松正人氏。
2月24日に開催されたJATA経営フォーラム2009のパネルディスカッションは、「旅行業、生き残り戦略とは!−他業種からヒントを掴め−」がテーマ。コメンテーターにはとバス代表取締役社長の松尾均氏、富士フィルムのヘルスケア事業統括本部ライフサイエンス事業部営業部長の杉本和繁氏、香港のEGL tours董事総経理の袁文英氏が出席し、各社が直面した経営危機と生き残り戦略について、興味深い経験を語った。異業種とはいえ、各社が経験した危機は旅行業界にとって人ごとではなく、各社のユニークな取り組みは今後の経営のヒントになり得るものが多かった。モデレーターを務めたのは、ツーリズム・マーケティング研究所の取締役マーケティング部長の高松正人氏。時代の流れや天災に翻弄されて経営危機に
 今年60周年を迎えるはとバスは、今や「プロが選ぶ観光バス30選」で日本一を受賞する優良バス会社。1960年から70年台は右肩上がりに業績を伸ばし、東京オリンピックの年には年間の利用者が122万人とピークを迎えた。しかし、旅行形態が団体から個人へ、ライフスタイルがバスからマイカーへ、そしてバブル崩壊という時代の変化に伴い、業績は徐々に下がり、04年には53万人にまで落ち込んで初の赤字決算を出したという。
今年60周年を迎えるはとバスは、今や「プロが選ぶ観光バス30選」で日本一を受賞する優良バス会社。1960年から70年台は右肩上がりに業績を伸ばし、東京オリンピックの年には年間の利用者が122万人とピークを迎えた。しかし、旅行形態が団体から個人へ、ライフスタイルがバスからマイカーへ、そしてバブル崩壊という時代の変化に伴い、業績は徐々に下がり、04年には53万人にまで落ち込んで初の赤字決算を出したという。1932年に創業した富士フィルムは、今年で75周年。日本を代表するフィルム会社だが、現在、同社のフィルムの取り扱いはわずか3%というのが現状だ。新しいフィルムやインスタントカメラのヒットなどで2000年までは右肩上がりだったという同社だが、同年以降にデジタル化の波が一気に押し寄せ、05年には写真関連事業が赤字に転じた。カメラのフィルムだけでなく、製版や刷版のフィルム、医療におけるレントゲンなど、あらゆるフィルムがデジタルに変わっていく流れは今も続いているという。
 香港の会社EGL toursは、日本への送客を専門とする旅行会社として出発。1986年の創業時に5名だった社員は650名となり、07年には高層の自社ビルが建つまでに成長した。オセアニアやアジアへも順次事業を拡大したため、阪神大震災や円高といった日本における危機だけでなく、スマトラ沖地震や四川大地震などの天災が起こるたびに危機に直面してきたという。しかし、最も大きな打撃を受けたのは03年のSARS。香港中が静まりかえり、旅行どころの話ではなくなったからだ。
香港の会社EGL toursは、日本への送客を専門とする旅行会社として出発。1986年の創業時に5名だった社員は650名となり、07年には高層の自社ビルが建つまでに成長した。オセアニアやアジアへも順次事業を拡大したため、阪神大震災や円高といった日本における危機だけでなく、スマトラ沖地震や四川大地震などの天災が起こるたびに危機に直面してきたという。しかし、最も大きな打撃を受けたのは03年のSARS。香港中が静まりかえり、旅行どころの話ではなくなったからだ。柔軟な方向転換で生き残りの道を模索
はとバスが事業の再生に乗り出したのは1998年。リストラを含む総合的なダウンサイジングや財政基盤を立て直す経営改革を実行したが、何よりも大きかったのは意識改革だ。松尾氏は「経営者を含む全社員が危機感をもち、原点に返ってお客様ありきの商売であることを確認した」という。具体的には月500通届くアンケートの声に耳を傾け、徹底したメンテナンスで安全の確保をはかり、またはとバスの文化を築いてきたと言ってもいいガイドの教育により一層力を入れたという。「数年前に刷新したパンフレットは、改めてお客様への想いを形にしたものとして、魂を込めている」といい、パンフレットは、“はとバスにしかできない商品づくり”の分かりやすい一例だ。
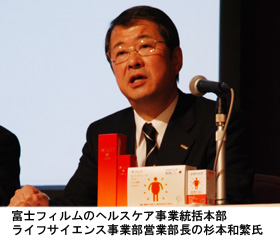 富士フィルムでは、04年を第2の創業の年ととらえ、写真事業の構造改革をおこなった。リストラや設備圧縮等をしたことで翌年には売り上げが前年の半分以下に落ち込んだが、光学デバイスやフラットパネルディスプレイなど成長事業に思い切った投資をしたことで、それらが実を結ぶ結果を出している。一方で研究所を拡大し、これまでにない事業を創造。それがスキンケア商品「アスタリスク」だ。「実はフィルムの主成分はコラーゲン。長年の研究により、この技術においては絶対の自信を持っている」(杉本氏)という同社から化粧品という商品が生まれても不思議ではなかったのだ。事業規模は決して大きくないが、売り上げは短期間で伸びた。しかし、「化粧品会社に変わるわけではなく、写真文化は永遠に守るという想いは持ち続けている」という。
富士フィルムでは、04年を第2の創業の年ととらえ、写真事業の構造改革をおこなった。リストラや設備圧縮等をしたことで翌年には売り上げが前年の半分以下に落ち込んだが、光学デバイスやフラットパネルディスプレイなど成長事業に思い切った投資をしたことで、それらが実を結ぶ結果を出している。一方で研究所を拡大し、これまでにない事業を創造。それがスキンケア商品「アスタリスク」だ。「実はフィルムの主成分はコラーゲン。長年の研究により、この技術においては絶対の自信を持っている」(杉本氏)という同社から化粧品という商品が生まれても不思議ではなかったのだ。事業規模は決して大きくないが、売り上げは短期間で伸びた。しかし、「化粧品会社に変わるわけではなく、写真文化は永遠に守るという想いは持ち続けている」という。SARSに打ちのめされて1ヶ月以上が経った時、EGL toursが打ち出したのは実にユニークなツアーだった。それは、香港の人々が香港を旅行する88ドルの日帰りツアー。袁氏は「国内に目を向け、外に出たい、遊びたいという人々の気持ちを刺激したことでこのツアーは当たった」と説明。まさに発想の転換で、社員は毎日出発する日帰りツアーのバスを外に出て見送ったという。袁氏はこの“見送り文化”を日本で学んだといい、こうしたきめ細かな接客がその後のリピーター育成につながっていると話した。
ヒントは自社の財産の中にこそ潜む
はとバスは徹底したCS(顧客満足)に目を向け、事業再生に10年間を費やした。松尾氏が「潜在事業である“旅”をいかに顕在化していくか、要は生身の人間力の成せる業」というように、同社の基盤となったのは人だった。また富士フィルムは、「自社の資源を今一度見直し、それをどう活用していくか」(杉本氏)が大切だとし、フィルム技術から化粧品を生み出すという予想外の事業を展開した。さらにEGL toursは、袁氏が「危機の時こそ自分より他人のことを考えてやってきた」というように、被災地に人を送り続けることで復興を助け、自社だけでなく旅行業界全体に貢献しながら、時代をたくましく生き残ってきた実例を示している。
取材:竹内加恵