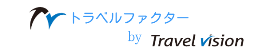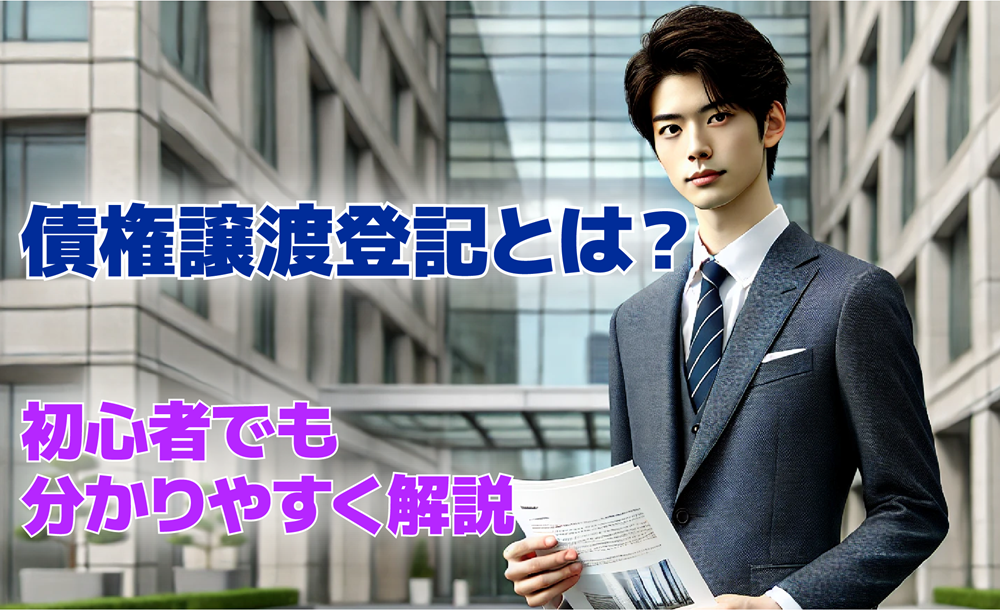
「債権譲渡登記とは?」
「債権譲渡登記はどんな場面で使えるのか?」
債権譲渡登記に対してこうした疑問を持っているのではないでしょうか?
当記事では、債権譲渡登記について分かりやすく解説し、その有用性や申請方法、それに要する費用などについても詳しく触れていきます。
債権譲渡登記とは?初心者でも分かりやすく解説
目次
債権譲渡登記とは、債権を譲渡する際にその事実を法的に明確にするための登記のことです。
これを行う事により、当事者以外の第三者にもその事実が認められ、新たな債権の所有者はその権利を法的に保護してもらえます。
参考:国税庁(債権譲渡の意義)
ファクタリングで債権譲渡登記が必要な理由
ファクタリングで債権譲渡登記が必要な理由は、債権譲渡があった事実を第三者に対して明らかにし、法的な権利を守るためです。
具体的な理由としては、主に下記が挙げられます。
- 第三者対抗要件を満たすため
- 他の債務者との優先順位を確保するため
- 債権の透明性を確保するため
- 債務者の支払先をはっきりさせるため
もしファクタリングで債権譲渡登記をしなかった場合は、二十譲渡をはじめとした様々なトラブルが起こり得ます。
その結果、新たな債権者は債権を回収できなくなりかねません。
債権譲渡登記は、そうしたリスクを避けたりするうえで必要になります。
ファクタリングの際に債権譲渡登記を用いるメリット
ファクタリングの際に債権譲渡登記を用いれば、主に下記のメリットが出てきます。
- ファクタリング会社は二重譲渡のリスクを回避できる
- ファクタリング利用者は取引先に知られることなく資金調達できる
- ファクタリング手数料が引き下がる可能性がある
- 審査通過率が上がる
- 悪質ファクタリング業者を避けられる
以下では、それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。
ファクタリング会社は二重譲渡のリスクを回避できる
ファクタリングの際に債権譲渡登記を用いた場合、ファクタリング会社にとっては主に下記のリスクを回避できるメリットがあります。
| ファクタリング会社のリスク | 詳細 |
|---|---|
| 二十譲渡リスク | 複数の債権譲渡が行われた場合、後から譲渡を受けた債権者(他のファクタリング会社など)が先に登記を行えば、その債権を回収できる権利を失うリスク |
| 優先権を失うリスク | 複数の債権譲渡が行われた場合、対抗要件を満たしていないため、登記や通知を行った他の債権者の方が優先されてしまうリスク |
| 債務者による異議申し立てリスク | 債務者に債権譲渡の通知がなかった場合で、債務者が元の債権者である譲渡人に支払いをした場合、その譲渡人による正当な支払いだとする主張がまかり通るリスク |
債権は目に見えない資産です。
もし、債権譲渡登記なしでファクタリング取引を行った場合、売掛債権の所有権が誰なのかを示す根拠が法的に不十分であり、二重譲渡などのリスクが起こりえます。
例えば、悪質業者がいた場合、その業者がインチキをして特定の売掛債権を複数のファクタリング業者に現金化を依頼すれば、二重譲渡が発生します。
そうなった場合、ファクタリング会社側としては、売掛金を回収できなくなり損失を被りかねません。
しかし、ファクタリング契約の際に債権譲渡登記を行っていれば、売掛債権の所有権が法的に担保されるため、基本的に二重譲渡が発生しなくなります。
そのため、ファクタリング会社としては、債権譲渡登記を行う事で、二重譲渡による債権の未回収リスクを回避できるわけです。
二重譲渡以外のトラブルに関しても、債権譲渡登記を行っていればすべて回避できます。
ですので、ファクタリング会社は、債権譲渡登記を行うことで、債権の未回収リスクを最小限に抑えられます。
ファクタリング利用者は取引先に知られることなく資金調達できる
ファクタリングの際に債権譲渡登記を行えば、ファクタリング利用者にとっては、取引先(売掛先)に知られることなく資金調達ができるのも利点です。
債権譲渡登記なら、債務者には知られずに債権を譲渡できるので、その取引先の信頼性などを失うことなくファクタリング取引ができます。
とはいえ、債権譲渡登記のデータは法務局で公に公開されるので、確認されれば取引先に債権譲渡を行った事実が知られるでしょう。
これにより、自社の経営状態が良くないのではないかと知られる恐れが出てきます。
しかし、登記データを閲覧するにも費用がかかるので、結局取引先に債権譲渡をした事が判明する可能性は低いです。
ファクタリング手数料が引き下がる可能性がある
ファクタリングの際に債権譲渡登記を行えば、ファクタリング利用者側にとっては、その手数料が引き下がる可能性が大いににあるのもメリットだと言えるでしょう。
債権譲渡登記をすれば、売掛債権の所有権が法的に明確に示されるので、ファクタリング会社の権利が保証されます。
これにより、ファクタリング会社は、売掛債権の未回収リスクを極端に減らす事が可能。
ファクタリング取引における手数料は、未回収リスクの大きさによって決まるので、債権譲渡登記によりこのリスクが大きく減り、手数料の引き下げが可能になるわけです。
手数料が下がれば、その分多くの資金調達が実現されるため、資金繰りをするうえで有利に働くでしょう。
審査通過率が上がる
ファクタリング時に債権譲渡登記を行った場合、ファクタリング利用者にとっては、契約時に必要な審査ハードルが下がるのも利点です。
債権譲渡登記を用いれば、売掛債権の所有権が保護され、売掛債権の回収の目途が十分に立ちます。
これにより、ファクタリン会社としては、「取引してもリスクが少ない」と判断できる事から、審査に通りやすくそれに要する時間も短くて済みます。
悪質ファクタリング業者を避けられる
ファクタリング取引の際に債権譲渡登記を行えば、ファクタリング利用者にとっては、悪質ファクタリング業者を避けられるのもメリットです。
債権譲渡登記の手続きを踏む際は、「代表者の資格証明書」をはじめとした、しっかりとした身元確認の書類の提出が必須です。
もし、契約しようとしているファクタリング会社が怪しい業者なら、資格証明書を取得したりするのが難しいでしょう。
ですので、債権譲渡登記も困難となり、それが判明すれば悪徳業者だと疑われます。
このように、債権譲渡登記を用いれば、怪しい業者を回避できるのも利点です。
ファクタリングの際に債権譲渡登記を用いるデメリット
一方で、ファクタリングの際に債権譲渡登記を行った場合、主に下記のデメリットがある点には注意してください。
以下では、それぞれのデメリットについて解説していきます。
登記を行う際に登記費用がかかる
ファクタリングの際に債権譲渡登記を用いる場合、登記費用として7,500円~15,000円程度の費用がかかります。
また、司法書士に登記の申請を依頼した場合は、4~10万円の費用も発生します。
ファクタリングは資金繰りをするうえでは役立ちますが、債権譲渡登記をするとなれば、別途こうした費用が発生する点には注意してください。
手続き完了までに一定の期間を要するのですぐに現金化できない
債権譲渡登記を行う際は、その手続きが完了するまでに一定の期間(2日~4日)を要するのもネックです。
そのため、ファクタリングで債権譲渡登記を用いる場合は、即日での売掛債権の現金化が厳しくなります。
個人事業主は債権譲渡登記ができない
債権譲渡登記はあくまでも法人でしか行えず、個人で行う事はできません。
ですので、個人事業主でファクタリングをする場合、そもそも債権譲渡登記ができません。
もし、個人事業主でファクタリングがしたいなら、債権譲渡登記なしの業者を選ぶなりする必要があります。
金融機関で融資を受ける際の審査に影響が出る可能性がある
債権譲渡登記を行うと、金融機関で融資を受ける際の審査に影響が出てくる可能性があります。
というのも、金融機関で融資の審査をする際に、過去に債権譲渡登記をしたかどうか調査されるケースもあるからです。
このような場合は、過去にした債権譲渡登記が金融機関での融資の可否を左右することにもなりかねません。
債権譲渡登記の必要書類
登記には下記の種類があります。
| 登記の種類 | 内容 |
|---|---|
| 債権譲渡登記/質権設定登記 | 債権譲渡の事実を第三者に対して法的に証明にするのに必要な登記 |
| 延長登記 | 債権譲渡登記/質権設定登記の存続期間を延長するのに必要な登記 |
| 抹消登記/一部抹消登記 | 債権譲渡登記/質権設定登記を抹消する場合に必要となる登記 |
以下からは、それぞれの登記における必要書類について詳しく解説します。
債権譲渡登記/質権設定登記
債権譲渡登記/質権設定登記における必要書類は下記の通りです。
- 登記申請書
- 代理権限証書(手続きを委任する場合に必要)
- 取下書(提出は任意)
- 申請データを記録した電磁的記録媒体(CD-R又はCD-RW)(オンライン申請/事前提供方式申請時は不要)
- 譲渡人の代表者の資格証明書(作成後3カ月以内のもの)
- 譲渡人の代表者の印鑑証明書(作成後3カ月以内のもの)
- (譲受人が法人の場合)譲受人の代表者の資格証明書(作成後3か月以内のものに限る)/(譲受人が自然人の場合)譲受人の住所を証する書面(住民票の写し)
- 存続期間が登記の日から50年(債務者不特定の債権を含む場合には10年)を超えるときは、その存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面
登記申請書に関しては、法務省に記載されている申請書のひな形をダウンロードすれば簡単に作成可能です。
代理権限証書は、債権譲渡登記の手続きを司法書士などに依頼する場合に必要となります。
取下書の提出は任意ですが、添付しておくと登記申請に間違いがあって申請が却下されたときに、収入印紙が戻らなくなる事を防げます。
その他、状況に応じて別途書類が必要となるケースもあります。
司法書士に依頼すれば、必要書類としては、代理権限証書、登記事項証明書の取得に関する委任状、譲渡人の代表者の資格証明書、譲渡人の代表者の印鑑証明書だけで済みます。
延長登記
延長登記の必要書類は下記の通りです。
- 延長登記申請書
- 代理権限証書(手続きを委任する場合に必要)
- 取下書(提出は任意)
- 申請データを記録した電磁的記録媒体(CD-R又はCD-RW)(オンライン申請/事前提供方式申請時は不要)
- 譲渡人の代表者の資格証明書(作成後3か月以内のものに限る)
- 譲渡人の代表者の印鑑証明書(作成後3か月以内のものに限る)
- (譲受人が法人の場合)譲受人の代表者の資格証明書(作成後3か月以内のものに限る)
- 譲受人(質権者)又は譲渡人(質権設定者)の表示が登記された表示と異なるときは、その変更を証する書面
- 存続期間が登記の日から50年(債務者不特定の債権を含む場合には10年)を超えるときは、その存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面
抹消登記/一部抹消登記
抹消登記の必要書類は以下の通りです。
- 抹消登記申請書(または一部抹消登記申請書)
- 代理権限証書(手続きを委任する場合に必要)
- 取下書(提出は任意)
- 申請データを記録した電磁的記録媒体(CD-R又はCD-RW)(オンライン申請/事前提供方式申請時は不要)
- 譲渡人(質権設定者)の代表者の資格証明書(登記事項証明書。作成後3か月以内のものに限る)
- 譲受人(質権者)の印鑑証明書(法人の場合は登記所が作成したもの。自然人の場合は市町村長が作成したもの。いずれも作成後3か月以内のものに限る)
- (譲受人が法人の場合)譲受人(質権者)の代表者の資格証明書(登記事項証明書。作成後3か月以内のものに限る)
- 譲受人(質権者)又は譲渡人(質権設定者)の表示が登記された表示と異なるときは、その変更を証する書面
債権譲渡登記の費用
債権譲渡登記にかかる費用は、大まかに下記の通りになります。
| 内訳 | 費用 |
|---|---|
| 登録免許税(債権譲渡登記) | 7,500円~15,000円 |
| 司法書士への報酬 | 40,000円~100,000円 |
債権譲渡登記を自力で行う場合は登録免許税のみで可能です。
司法書士に依頼する場合は、別途費用がかかりますが、手続きに要する時間的なコストを大幅に省けます。
債権譲渡登記の登録免許税
債権譲渡登記(延長登記や抹消登記含む)における登録免許税の詳細は下記の通りです。
| 登記の種類 | 登録免許税 |
|---|---|
| 債権譲渡登記/質権設定登記 | ・債権個数が5,000個以下:1件につき7,500円 ・債権個数が5,000個を超える場合:1件につき15,000円 |
| 延長登記 | 1件につき3,000円 |
| 抹消登記/一部抹消登記 | 1件につき1,000円 |
債権譲渡登記に記載される内容一覧
ファクタリングにおける、債権譲渡登記に記載される内容は下記の通りになります。
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 登記の目的 | 債権譲渡登記 |
| 譲渡人の情報 | ファクタリング利用者の情報(会社名や住所など) |
| 譲受人の情報 | ファクタリング会社の情報(会社名や住所など) |
| 登記原因日付 | 債権譲渡契約が成立した日付 |
| 登記の原因 | 売買 |
| 債権の総額 | ファクタリングの売掛債権の総額 |
| 原債権者 | 債権発生当時の債権者の情報(会社名や住所など) |
| 債務者 | 売掛先の情報(会社名や住所など) |
| 債権の種類 | 基本的に「売掛債権」 |
| 発生時債権額 | 取引によって発生した債権額 |
| 譲渡時債権額 | ファクタリングした債権額 |
債権譲渡登記の申請方法
ここからは債権譲渡登記の申請方法について詳しく解説します。
債権譲渡登記の申請方法
債権譲渡登記を申請するには、譲渡人と譲受人の共同で行います。
また、債権譲渡登記の申請方法は主に下記の4つがあります。
- 登記所への出頭による申請
- 郵送による申請
- オンライン申請
- 事前提供方式
「オンライン申請」や「事前提供方式」では、申請データを記録した電磁的記録媒体(CD-R)の添付が不要なため、コスト削減につながるでしょう。
「オンライン申請」と「事前提供方式」の違いは、オンライン申請が登記に必要な情報すべてをオンラインで送信する方式なのに対し、事前提供方式は従来方式で必要な申請データはオンライン上で送信し、登記申請書や添付書面は別途書面で提出する方式になります。
債権譲渡登記の申請の流れ
債権譲渡登記の申請の流れは、主に下記の通りになります。
-
STEP1必要書類を用意する上記で紹介した必要書類(直接出頭または郵送での手続きに限り申請データを記録した電磁的記録媒体(CD-R又はCD-RW)を添付)を用意します。
-
STEP2必要書類を法務局に提出する手続きに必要な書類を東京法務局民事行政部債権登録課に提出します。
債権譲渡登記をスムーズに進めるポイント
債権譲渡登記の手続きを自力で行う場合、必要書類を確認してすべてを用意するのが大変です。
しかし、司法書士に依頼すれば、手続きを任せられるのでスムーズです。
司法書士に依頼する場合は、別途費用がかかりますが、申請を簡潔に済ませたいのであれば、委任する価値はあるでしょう。
債権譲渡手続きで必要となる対抗要件の詳細
債権譲渡を行う際は、債権譲渡契約を締結したうえで、第三債務者や第三者に対して対抗要件を具備する必要があります。
対抗要件とは、譲渡人・譲受人で交わされた債権譲渡の事実を第三債務者や第三者に対して法的に証明するための条件のこと。
これは、第三債務者と第三者のそれぞれに対して具備する必要があります。
以下では、「第三債務者に対する対抗要件」と「第三者に対する対抗要件」についてそれぞれ解説します。
第三債務者に対する対抗要件
譲受人が問題なく譲渡された債権を回収するためにも、第三債務者(譲渡人とは別の債務者)に対して対抗要件を満たす必要があります。
第三債務者に対して対抗要件を満たすには、譲渡人が債権譲渡したことをその第三債務者に対して通知または承諾してもらう事で可能です。
これによって、新たな債権者となった譲受人は、第三債務者に対して取り立てを行った場合に、問題なく債権を回収できるようになります。
第三者に対する対抗要件
二十譲渡を防ぐためにも、第三者(債務者の他の債権者など)に対しても対抗要件を満たす必要があります。
第三者に対して対抗要件を満たすには、まず第三債務者に債権譲渡を承諾してもらいます。
次に、債権の譲渡人・譲受人の間で交わした債権譲渡契約の内容を、内容証明郵便で第三債務者に送ります。
その後、債権譲渡登記を行えば、債権譲渡を行った事実を法的に示すことができ、第三者に対する対抗要件に備えられます。
参考:e-GOV 法令検索
債権譲渡登記を行う際の注意点
債権譲渡登記を行う際は下記の点に注意しておきましょう。
登記可能な債権なのかをしっかり確認しておく
債権譲渡登記を行う際は、まずその債権が登記可能なのかどうかを確認してください。
というのも、債権の中には登記ができないものもあるからです。
例えば、債権譲渡禁止特約が交わされている債権なら、登記ができません。
そうした債権を登記する場合は、債権譲渡禁止特約を外す手続きが必要になりますが、その際に売掛先にファクタリングが知られてしまいます。
こうなると売掛先の信用が低下しかねません。
債権譲渡登記を行うときは、債権が問題なく登記可能なのかを把握しておきましょう。
ファクタリング後は債権譲渡登記の抹消を行う
ファクタリングで債権譲渡登記を行った場合は、ファクタリング完了後に債権譲渡登記の抹消手続きを行いましょう。
もし債権譲渡登記を抹消せずにいると、以後別のファクタリング会社と契約する際に、同じ債権を譲渡されていると判断され、審査に通過できなくなりかねません。
こうしたトラブルを避けたいなら、ファクタリング完了後は早急に債権譲渡登記の抹消手続きを行ってください。
債権譲渡登記の確認方法や閲覧方法
ここからは債権譲渡登記の確認方法や閲覧方法について解説していきます。
債権譲渡登記の確認方法
債権譲渡登記の内容を確認できる書類は「登記事項証明書」「登記事項概要証明書」「概要記録事項証明書」の3つの種類があります。
それぞれの書類の内容や確認可能な人物、請求先は以下の通りです。
| 登記証明書の種類 | 証明書の内容 | 請求可能な人物 | 手数料 | 請求先 |
|---|---|---|---|---|
| 登記事項証明書 | 債権譲渡登記の詳細情報 | 当事者のみ | 債権1個につき500円 (債権2個以上の場合は、1債権追加ごとに+200円) |
東京法務局民事行政部債権登録課 |
| 登記事項概要証明書 | 債権譲渡登記の大まかな情報 | 誰でも | 1通300円 | 東京法務局民事行政部債権登録課 |
| 概要記録事項証明書 | 該当企業が譲渡人となっている債権譲渡登記の有無 | 誰でも | 1通300円 | 全国の法務局 |
債権譲渡登記の閲覧方法
債権譲渡登記を閲覧する場合は、下記の方法で可能です。
- 法務省の登記情報提供サービスを利用する(ネットで可能)
- 各種証明書を取得する(証明書を郵送してもらう)
登記情報提供サービスを利用すれば、ネット上で債権譲渡登記の情報が閲覧できます。(平日8:30分~21:00、土日祝8:30分~18:00)
また、各種証明書を取得する場合は、下記の方法で申請が可能です。
- 窓口申請
- 郵送申請
- オンライン申請
債権譲渡登記に関するよくあるQ&A
- 債権譲渡登記は何のためにするのですか?
- A:第三者に対して債権譲渡の確実性を法的に担保するために行われます。これにより、二重譲渡をはじめとした様々なトラブルを回避しつつ、安全・確実な債権の譲渡が可能になります。
- 債権譲渡されたらどうなる?
- A:譲受人が新たな債権者となり、譲渡人(債務者)に対して債務を請求できる権利が持てます。
- 債権譲渡 何のために?
- A:債権譲渡は様々な目的で行われます。具体的には企業の資金調達(ファクタリング)や債権を持ち続けるリスクを回避する目的などで行われます。
- 債権譲渡登記の金額はいくらですか?
- A:登録免許税として7,500円~15,000円かかります。また、司法書士に依頼する場合は4万円~10万円程度かかります。